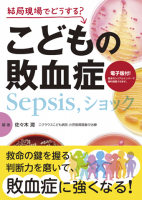お知らせ
吃音(小児期発症流暢症)[私の治療]
吃音症は,呼吸器や発声・発語器官に器質的・機能的異常がないのに,後に述べる吃音中核症状が発話時に生じる障害である。小児の場合,言語発達の途上で生じる発達性吃音が大部分を占める。遺伝子の関与や脳内接続性の問題などが原因として考えられている。2016年から行われたわが国の調査研究では,3歳時の吃音の有症率は4~5%,3歳までの累積発症率は8~9%,5歳頃までの治癒率は75%程度であることが報告されている。
▶診断のポイント
吃音は症状診断である。吃音の診断は,音,モーラ,音節,語の一部などの繰り返し(連発),音,音節が他の音節の長さと比較して不自然に長くなる引き伸ばし(伸発),語頭や語中で言葉を出そうとして出せないブロック(難発)の中核症状の有無と頻度で診断を行う。また,中核症状に加えて,発話の際に手足や頭を動かす,息を吸い込んでから発話するなどの随伴症状を伴うことがある。幼児期の吃音は症状の変動が大きく,一時点の検査のみで診断することのないように注意が必要である。一方,学童期や中高生になると,中核症状が目立たなくなる一方で,吃音に対する悩みや不安が増加する,他人とのコミュニケーションに不安や負担を感じるなどの心理症状が強くなることも認められる。必要に応じて,社交不安障害やうつの状態を評価する。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
吃音の治療の一般的な流れは,①経過観察,②環境調整,③直接的介入,となる。先に述べたように,幼児の吃音は罹患率が高い一方で自然治癒率も高い。このため,発症早期からの積極的な介入の必要はないと言える。まずは自然経過の観察を行い,吃音中核症状が1年以上継続する,症状が重篤である,保護者の不安が強い場合などは,専門的な対応ができる施設へ紹介すべきと考える。
対応としては,患者の吃音重症度や心理的側面などを評価した後,環境調整法を数カ月実施する。改善が得られないようであれば,環境調整法は継続しつつ,流暢性形成法,リッカム・プログラムなどの直接的訓練を実施する。
一方,中高生の吃音では,既に症状が継続しており,心理的にも負担がかかっている事例が多いため,幼児とは異なる対応が必要である。直接法(流暢性形成法,吃音緩和法)や,シャドーイング,メンタルリハーサル法,認知行動療法などを用いて治療を行う。

残り930文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する