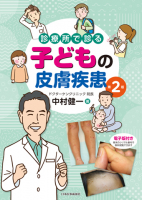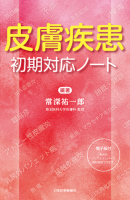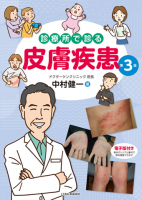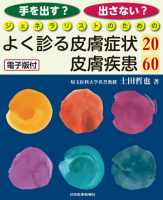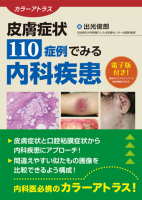お知らせ
シラミ症[私の治療]
シラミには,アタマジラミ,ケジラミ,コロモジラミがいる。アタマジラミは頭髪に,ケジラミは陰毛・腋毛に,コロモジラミは衣類に寄生する。種類や寄生する場所は異なるものの,どのシラミもヒトの血を吸い生きている。雌成虫が毛に卵を産み,ふ化した幼虫は,ヒトの皮表で血を吸いながら成虫となり,また卵を産む。このようにシラミは一生をヒトの皮表で過ごす。その間,接触の機会があると他のヒトにも感染する。アタマジラミ症は保育所・幼稚園や小学校など集団生活を送る場所で多く発生する。患者数は,コロナ禍前は年間50万~100万人と推測されていた1)。コロナ禍にアタマジラミ症の患者数は一時減少していたものの,再び増加の兆しがある。ケジラミ症は,第二次性徴の陰毛や腋毛に寄生し,また性感染症の側面もあることから,思春期以降に多い。コロモジラミ症は,いにしえから第二次世界大戦頃まで日本全国に蔓延していたが,戦後の衣住環境の改善に伴い激減した。今ではホームレスを除いて稀である。
▶診断のポイント
アタマジラミ,ケジラミの診断は,虫体や毛についた虫卵を見つけることである。虫卵と紛らわしいものに,ヘアキャストと言われる鞘状のフケがある。虫卵は毛に固着して動かないのに対し,ヘアキャストは毛の上で引っ張ると前後にするする移動する。

▶私の治療方針・処方の組み立て方
市販のシラミ用ピレスロイド系殺虫薬(フェノトリン)を用いる。薬剤は虫卵には効果が乏しいため,卵がふ化する頃に繰り返し使用する。治療すると虫体は死滅するが,卵の抜け殻だけは毛に残る。抜け殻を卵と誤解しないようにする。
治療をしても治らないケースがあり,近年増えている。その原因は,薬剤(フェノトリン)抵抗性アタマジラミである。沖縄県ではほぼ100%が薬剤抵抗性と言われている2)。フェノトリンを使用しても虫体が見つかる場合には,別の治療が必要となる。ジメチコン製剤(ジメチルポリシロキサン)か,梳き櫛である。

残り1,003文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する