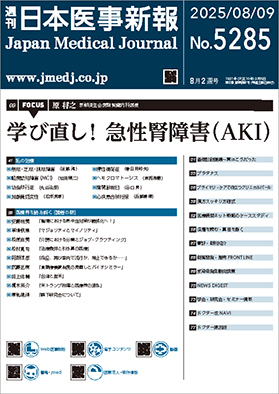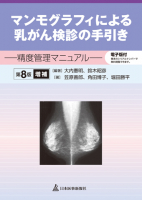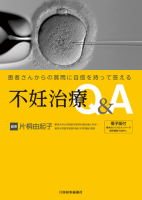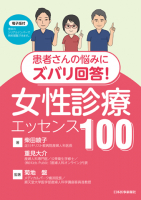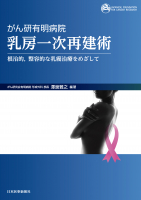お知らせ
乳癌治療後の妊娠・出産

【Q】
乳癌治療後に患者さんが妊娠・出産を希望する場合,どのような指針に沿って情報提供を行っておられますか(特にホルモン感受性陽性乳癌での適応について)。海外の動向についても併せて,国立がん研究センター中央病院・清水千佳子先生のご教示をお願いします。【質問者】
渡邊知映:上智大学総合人間科学部看護学科准教授
【A】

妊娠・出産に関する意思決定は個人的なものであり,医療者がパターナリズムで意思決定をするわけにはいきません。生殖年齢にある患者さんには,患者さんの意思表示の有無によらず,治療開始前にがん治療が妊孕性に与える影響や妊孕性保持の可能性についてお話しすることが大切です。
国内では2014年9月に医療者から患者さんへの情報提供を支援するため,『乳がん患者の妊娠出産と生殖医療に関する診療の手引き(2014年版)』(金原出版)が発行されました。こうした情報を参考に,がんの予後,治療の効果,生殖機能に与える影響,生殖医療の成績など,患者さんの意思決定に必要な情報を,現時点では不明な点も含め,正確にわかりやすく伝える必要があります。
がん治療の側面からだけを考えますと,閉経前ホルモン受容体陽性乳癌の患者さんには,術後に5~10年にわたるタモキシフェンの投与が推奨されています。タモキシフェンは流産や催奇形性のリスクがあるため,内服中および薬剤が体内からwash outされるまでの数カ月間は避妊が必要になります。したがって,がん治療を最優先にしていると,ホルモン療法終了時には年齢的に妊娠・出産の機会を失ってしまう可能性があります。
妊娠・出産のためにタモキシフェンの投与を延期したり,中断したりすることが,がんの予後に不利益をもたらすかどうかはわかっていません。
現在,International Breast Cancer Study Group(IBCSG)を中心に,閉経前ホルモン受容体陽性乳癌患者が妊娠・出産のために一時的にホルモン療法を中断することの安全性を評価することを目的とした世界規模の臨床研究Pregnancy Outcome and Safety of Interrupting Therapy for Women With Endocrine Responsive Breast Cancer (POSITIVE)試験(IBCSG48-14/BIG8-13)が開始されたところであり,わが国でも参加の準備を進めています。