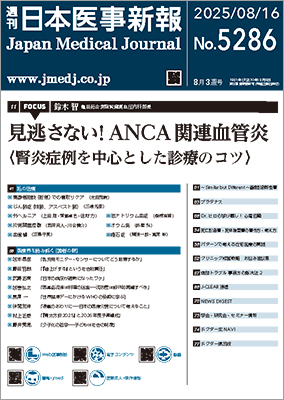お知らせ
肺アスペルギルス症の診断

アスペルギルス(Aspergillus)が引き起こす肺感染症は,発症の機序により急性と慢性に分類される。これまで慢性発症の病型には,内科的な視点だけでなく,病理学的もしくは放射線学的な視点から分類された病型が混在しており,中には実地臨床では鑑別が困難な病型も存在していたため,診断や治療に混乱が生じていた。このため,2014年に改訂された『深在性真菌症の診断・治療ガイドライン』(文献1)では,診断や治療を整理する試みがなされた。このガイドラインでは,慢性の病型を単純性肺アスペルギローマ,慢性進行性肺アスペルギルス症の2型のみとし,診断や治療までの流れをフローチャート式にすることで,より臨床に即した内容となった。
肺アスペルギルス症は,培養や組織検査での菌体の証明,もしくは血中β-D-グルカンやガラクトマンナン抗原,抗アスペルギルス沈降抗体により診断がなされるが,いずれの検査も感度や特異度,保険適用の面で問題が残る。
近年,アスペルギルスから分泌される糖蛋白に対するモノクローナル抗体を用いたlateral flow deviceが開発され,血清や気管支肺胞洗浄液を用いた研究が進められている(文献2)。定量測定はできないが15分で測定が可能であるため,特に迅速な診断を必要とする侵襲性肺アスペルギルス症での有用性が期待されている(文献3)。
【文献】
1) 深在性真菌症のガイドライン作成委員会, 編:深在性真菌症の診断・治療ガイドライン2014. 協和企画, 2014.
2) Prattes J, et al:Am J Respir Crit Care Med. 2014;190(8):922-9.
3) Eigl S, et al:Crit Care. 2015;19:178.