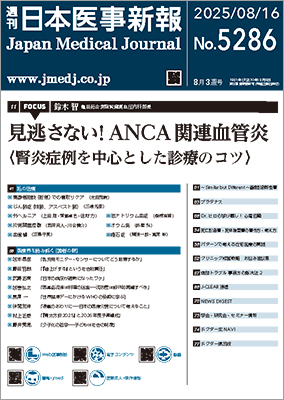お知らせ
非結核性抗酸菌症治療における副作用対策 【3剤併用療法で副作用が問題となる場合は,クラリスロマイシン+エタンブトールの2剤併用療法や間欠治療も視野に入れて治療】

非結核性抗酸菌症は結核菌群とらい菌群以外の抗酸菌による感染症で,わが国で最も頻度が高いのが,Mycobacterium avium症とM. intracellulare症を合わせたM. avium complex(MAC)症である。肺MAC症の標準治療はクラリスロマイシン(CA
M),エタンブトール(EB),リファンピシン(RFP)の3剤併用療法で,喀痰からの排菌陰性はおおむね70%程度で,しばしば再発する。治療期間は1~2年と長く,皮疹,胃腸障害,肝障害,視力障害などの副作用が問題になる。
CAM+EB+RFPの標準治療とCAM+EBの2剤による治療との比較試験において,治療完遂例における菌陰性化は前者の75.0%に対して,後者が82.5%であり,副作用による投薬中止例は後者で少なかった(文献1)。また,結節・気管支拡張型の肺MAC症に対する連日治療と週3回投与の間欠治療の比較において,菌陰性化は連日治療76%に対し,間欠治療67%と有意差を認めなかったが,連日治療でのEB中止例が24%に対し,間欠治療では1%と有意に低かった(文献2)。副作用が問題となる例では,このような治療を試みてよいかもしれない。
治療効果の改善のために,新たな薬剤の開発が望まれている。
【文献】
1) Miwa S, et al:Ann Am Thorac Soc. 2014;11(1):23-9.
2) Jeong BH, et al:Am J Respir Crit Care Med. 2015;191(1):96-103.