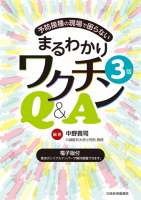お知らせ
都道府県間の健康格差に拡大傾向【渋谷健司東大院主任教授】
1990年以降日本の平均寿命や健康寿命は伸長している一方で、都道府県間の健康格差は拡大傾向にあることを、渋谷健司東大院主任教授らの研究グループが明らかにした。研究は日本時間の20日、オンライン版の『The Lancet』に掲載された。
研究では、東大院医学系研究科国際保健政策学教室と米ワシントン大学保健指標・保健評価研究所(IHME)が1990~2015年の日本の全国と47都道府県における各種健康指標の変化を分析した。その結果、25年間で平均寿命は4.2歳上昇(79歳から83.2歳)した一方で、都道府県の平均寿命の格差は2.5年から3.1年、健康寿命の格差は、2.3年から2.7年に拡大していることがわかった。
また、2015年の死亡のうち、33.7%は食習慣や喫煙等の行動習慣リスク、24.5%は高血圧や脂質代謝異常症等の代謝系リスク、6.7%は環境や職業上のリスクに起因することが判明。特に喫煙は男性において18.9%の死亡に寄与していることから、「最も主要なリスク要因」と問題視。タバコ対策は喫緊の課題だと指摘した。
都道府県間の健康格差の要因については、各都道府県の保健システムの主なインプット(1人当たりの医療費や人口当たりの医療人材)と保健アウトカム(年齢調整死亡率、疾病負荷)との間に有意な相関は見られなかった。同様に、リスク要因と都道府県間の健康格差でも顕著な相関が見られなかったとして、研究グループは、さらなる詳細な研究の必要性を指摘している。