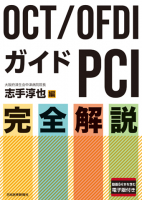お知らせ
(1)心房細動(AF)のとらえ方と治療の落とし穴[特集:これからの経口抗凝固薬(DOAC)処方のポイント]

心房細動(AF)は老化現象を基盤としており,単なる不整脈ではない側面がある
AFでは脳卒中以外の心血管死あるいは非心血管死も多い

早期にカテーテルアブレーションを行っても“根治する(=将来にわたって出ない)”わけではない
AF burdenを減らすことは,脳梗塞予防に有効な可能性はあるが検証が必要である
1. 心房細動(AF)の適切な診断のために
近年,心房細動(atrial fibrillation:AF)は,腎機能悪化やフレイルとの関連が指摘されており,決して単なる電気現象ではなく,老化・動脈硬化の類の全身的な変化の表現であるという側面を持つ1)。本稿では巷にあふれている「AFはカテーテルアブレーション(以下,アブレーション)を早期に行えば治る」「アブレーションしてしまえば治るので,発症しなかった人と同じにできる」かのごとき言説に警鐘を鳴らすとともに,AFをどのような病態と理解すれば,様々な臨床的課題に遭遇した際に,適切に判断していく上で役に立つかという視点で私見を交えて解説したい。
2. AFは心房の老化現象で,ほとんどは全身的な老化を伴う
AFの電気生理学的機序は,約1世紀前から様々な説が唱えられてきたが,それらは電気現象としてのAFの一面をとらえているにすぎない。AFの発症頻度は明らかに年齢依存性を呈している上,多くの研究で心房線維化との関連が示唆されている2)。つまりAFは加齢や高血圧といった基礎疾患に伴って発生する線維化を基盤として,つまり広い意味での“老化”を基盤として発生するのである。ある日突然,“正常な心房”の中に異常興奮する細胞群が現れ,AFを引き起こすというのではない。
しかし,肺静脈や上大静脈といった胸腔内大静脈が,異常興奮の発生場所となることが多いのは事実である。それらの異常興奮によってある程度の線維化・炎症が生じている心原での引き金が引かれ,AFが生じると,種々の実験で示されているように,心房の高頻度興奮のために線維化・炎症が一層進行する。その上,心房の拡大も生じるため,AFの基盤となる解剖学的・電気生理学的異常はさらに助長されることになる。これはかつて実験で示された,“AF begets AF(心房細動が心房細動を生む)”である。“AFは癖になる”といった感覚であろう。しかし注意するべきことは,薬剤やアブレーションによって,一時的に(かつ現実的には“一見”であるが)AFが出ていない状態になったとしても,“AF begets AF”による増加分が抑制されるだけであって,もともと進行していた背景の線維化を起こす“力”などは止まらないということである。「洞調律が続いていればどんどん心房は正常になって,AFとは無縁になる」というわけではない。“洞調律が洞調律を生む(SR begets SR)”は全体像を必ずしも正確に表現できていないのである。