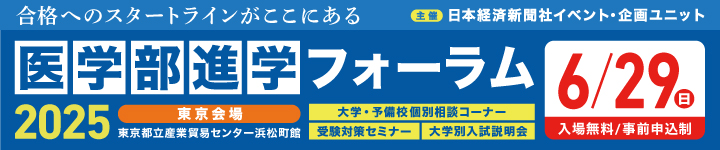お知らせ
動脈硬化評価目的の頸動脈エコーでコンサルトが必要な所見は?

透析クリニックで動脈硬化評価目的の頸動脈エコーを施行しています。50%以上の狭窄率を認めた場合,脳外科へコンサルトしていますが,ほかにコンサルトすべきプラークの性状等ありましたらご教示下さい。(愛知県 M)
【回答】
【プラークに部位,大きさ,表面,内部エコー,可動性など注意すべき所見や変化を認めた場合】

ご質問のように,症候の有無にかかわらず,狭窄程度が50%を超えたら,ドプラ法による病変の評価を行って,一度は専門医(脳神経内科・脳神経外科)へ相談して治療方針(侵襲的治療適応の有無)を確認することをお勧めします。その他に専門医へご紹介頂きたい項目としては,プラークに注意すべき所見や変化を認めたときです。詳細は,参考文献を参照頂きたいのですが,以下に要点を列記させて頂きます。
(1)プラーク
プラークとは,表面に変曲点を有する1.1mm以上の限局性隆起性病変を称していますが,1.5mm以下の小プラークは臨床的意義が少ないことから,1.5mm超のプラークに注目して評価をします。その評価項目としては,a存在部位(経過観察時に前回のプラーク部位と同じであると認定できるようにする)とともに,bプラークサイズ〔プラークを含めた最大計測値が最大内膜中膜複合体厚(max intima-media thickness:max-IMT)〕,c表面の形態(整,不整,潰瘍),d内部エコー性状(輝度,均質性),e可動性があります。
(2)注意すべきプラーク
プラークがあった場合は,十分な生活習慣病の治療を継続しつつ,そのサイズや性状により数カ月~1年ごとに観察して頂きます。プラーク評価で重要な項目は,脳梗塞との関連からは①「可動性」で,早々に専門医へ紹介して下さい。その他に②潰瘍形成,③薄い被膜,④低輝度プラーク(プラーク内に少しでも低輝度部分があれば,優先して「低輝度不均質」に分類しますが,石灰化による音響陰影によって評価できない場合は「評価不能」とします)がある例では,数カ月ごとに観察します。
(3)可動性に注意
「可動性プラーク」は,初見でも注意が必要です。可動性プラークの評価は,有茎性の可動性プラーク(floating plaque)やプラーク内部が拍動に伴って動揺する所見(jellyfish sign)などにわけられ,これらも塞栓症の再発に注意が必要であるため,専門医へ相談して下さい。
(4)観察中の変化に注意
数カ月ごとに観察をお勧めした②~④の所見があるプラークの例で,経過観察で注意して頂きたいのは,病変に「急速進行」(急速増大など)を認めた場合や「形状の変化」(潰瘍形成や突出像の出現など)が認められた場合です。その際も,速やかに専門医へ相談して下さい。
【参考】
▶ 日本超音波医学会:超音波による頸動脈病変の標準的評価法2017.
[http://www.jsum.or.jp/committee/diagnostic/pdf/jsum0515_guideline.pdf]
【回答者】
松尾 汎 松尾クリニック理事長