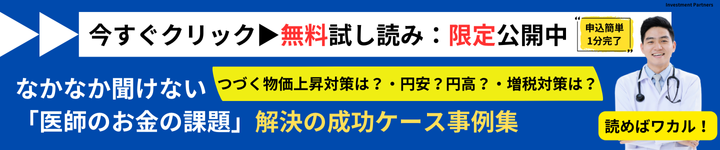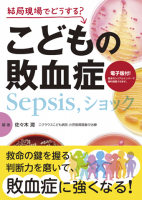お知らせ
【追悼】小児科医・川崎富作さん―全身の血管に炎症「川崎病」を発見
「自分の名の冠された疾患が外国の教科書に載る、これ以上の光栄はないですね」 (日本医事新報1988年10月29日号「人 川崎富作氏」より)
「自分の名の冠された疾患が外国の教科書に載るということは、一臨床家として、これ以上の光栄はないですね」
昭和36年1月、高熱、頸部リンパ節腫脹、結膜・口腔粘膜の充血、全身の発疹を伴い、しかも猩紅熱に似て非なる症状を呈した4歳3カ月の男の子が最初の症例。病原体もつかまらず、ペニシリンも効かない。では診断は何かとなると、「?」ということになってしまう。
この第一例の印象は強烈だった。「翌年、再び同様の患児に出会ったときは、ひそかな興奮さえ覚えた」という。
小児科学会千葉地方会、「アレルギー」誌に、「指趾の特異的落屑を伴う小児の急性熱性皮膚粘膜琳巴腺症候群」と題して発表したところが、全国から追加報告が相次ぐ。
後に、血栓閉塞から突然死に至ることもある重篤な疾患として、45年には、厚生省研究班が発足し、本格的な研究が始まった。
この「?」は若い川崎さんの脳裏を片時も離れなかった。ジュゲムジュゲム式の長い病名は、発見の名をとり“川崎病”と呼ばれるに至る。氏自身は、“川崎病”とは、こそばゆくて口にできずに、“その病気”とか“それ”とか代名詞を使ってしまうらしい。
発見から20年以上経た今でも原因は不明である。「何らかのごくcommonな感染微生物が引き金となって、ある特殊な体質を持つ子供に、免疫異常を起こす、という仮説が有力ですが」
一筋縄ではいかない川崎病の発症のメカニズムには、学問的にもユニークな医学上の問題をはらんでいる、何より世界の研究者を刺激するだけの新しい問題を提起した─これらの業績により、62年にベーリング北里賞、武田医学賞、そして今秋保健文化賞、日医医学賞をたて続けに授与される。
「臨床家の日常は、診察した患者に正しい診断をつけ、治療に専念することに尽きます」と言う。“猩紅熱に似て非なる疾患”は当初学会側から、類似の“Stevens-Johnson症候群”の一型とされるなど、認知に至る過程で紆余曲折があったことも否めない。しかし“診断がつかない”“未知なるもの”にこだわり続けた。
昭和23年千葉医大医専卒後、同大小児科に入局。2年後、日赤中央病院(現日赤医療センター)へ。後に愛育病院に移った内藤寿七郎、神前章雄、ペルガー氏家族性白血球核異常を発見した小久保 裕氏の個性的な3人の師と出会い、支えられ、以来、日赤を本拠に48年から小児科部長。
大正14年、東京・浅草生れ。ベーゴマ、メンコと聞くと身を乗り出す下町っ子。「海外出張の時はケン玉が必携。言葉のかわりにケン玉の妙技を披露して相手を煙に巻いてしまうんです(笑)」