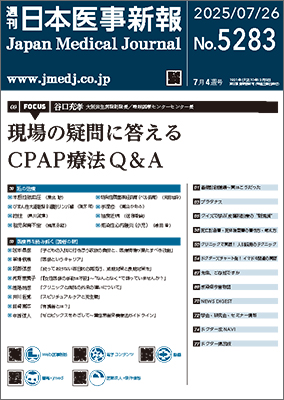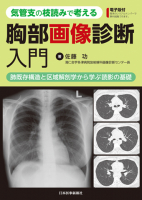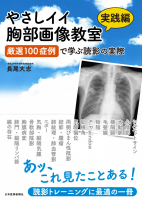お知らせ
特集:吸入療法ガイド─デバイス選択から吸入指導まで
近藤りえ子
1990年藤田保健衛生大学医学部卒業,呼吸器内科学Ⅱ講座に入局。2008年藤田保健衛生大学医学部客員准教授,近藤内科医院副院長。2015年近藤内科医院院長。2016年藤田保健衛生大学医学部客員教授
1 吸入指導の重要性
・ 吸入操作が間違っていると期待される効果が得られず,不要なstep upにつながる場合がある。
・ 良好なコントロールが得られない場合は,薬剤をstep upする前に吸入操作の再確認をする。
・ 特に高齢者において誤操作が目立つので,繰り返しの吸入指導が重要である。
・ 目で確認できない口腔内にも注意をはらい,「薬剤の通り道」をつくる必要がある。
・ 2020年4月より調剤報酬改定で吸入薬指導加算が算定できるようになった。

2 デバイスの種類・選択手順と操作手技(吸入指導DVDの活用)
・ わが国における現時点でのデバイスの種類は,11種類である。
・ 当教室でのデバイスの選択手順をフローチャートに示す。
・ 全国どの医療スタッフが吸入指導をしても漏れがないようにする目的で,「正しい吸入方法を身につけよう」と題した1枚の吸入指導DVDとポスターを作成し,無料で全国に配布できるようにした。
・ ポスターの裏面に「喘息発作時の家庭での対処方法」を収載し,説明を明解にした。
・ DVDは今後,患者指導のみでなく,新人の医療スタッフ・学生への教育にも有用である。
3 吸入指導のポイント
・ すべてのデバイスに共通した吸入指導のポイントを,初回指導時,すべてのデバイスの共通事項,2回目以降の3項にわけ,わかりやすくまとめた。
・ 間違っていた点はカルテに記録しておき,次回以降も注意深く見る。
・ 患者の努力により改善されていた点は,必ず褒めてあげることがアドヒアランス向上につながる。
4 吸入操作の間違えやすい点と対策
・ 各種デバイスにおける問題点と対策を表にまとめた。デバイスの選択手順と合わせ,患者の背景因子に合ったデバイスを選択する。
・ 説明時間が十分にとれない場合には,吸入指導DVDの視聴を勧める。
・ 加圧噴霧式定量吸入器(pMDI)の同調が困難な症例には,スペーサーを使用してもらう
・ 週1回のスペーサーの洗浄方法を説明することも大切である。
5 吸入時のベストな舌の位置(ホー吸入)
・ 口腔内の薬剤の通り道には舌が存在するので,吸入時には舌をなるべく下げ,喉の奥を広げて吸入することが重要である。
・ 舌を下げるテクニックを動画で解説する。「ホー吸入」と命名した。
・ 「ホー吸入」は,すべての吸入薬に共通したテクニックであり,追加コスト0円である。
6 外来での吸入指導の流れ
・ 初回指導時,再診時にわけ,流れを解説する。
・ 初回指導だけでは不十分であり,再診時に何回も繰り返す。
・ 吸入指導を繰り返しても良好なコントロールが得られない場合には,難治性喘息として次のステップに進む。