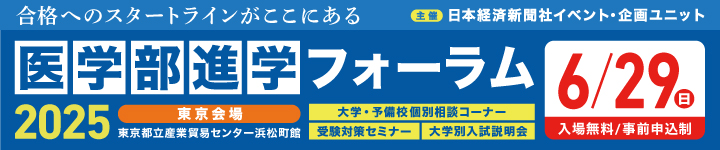お知らせ
■NEWS 【欧州心臓病学会(ESC)】安定冠動脈疾患に対する低用量コルヒチンのCVイベント抑制作用を、二重盲検試験で確認:LoDoCo2試験

2017年に報告されたCANTOS試験で、インターロイキン-1βを標的とするカナキヌマブによる動脈硬化性イベント抑制が示されて以来、抗炎症療法による冠動脈疾患治療に関心が集まっている。本学会では、わが国では痛風発作などに用いられているコルヒチンの安定冠動脈疾患例に対する有用性が、ランダム化試験“LoDoCo2”として発表された。ジェネシスケア(豪州)のMark Nidorf氏が報告した。
安定冠動脈疾患例に対するコルヒチンの心血管系(CV)イベント抑制作用はすでに、非盲検化試験“LoDoCo”で示されている。今回はその結果を、二重盲検試験で確認する形となった。LoDoCo2試験の対象は、6カ月間以上状態が安定していた冠動脈疾患例である。重症腎疾患、心不全、重度弁膜症の合併例は除外された。参加適格者は全例、コルヒチン0.5mg/日を30日間服用し、忍容可能(91.3%)で試験参加意思を有した5522例が、コルヒチン0.5mg/日群とプラセボ群にランダム化された。

患者の平均年齢は66歳、約85%が男性だった。また85%に急性冠症候群(ACS)の既往があったが、その7割弱は2年以上前に発症したものだった。治療薬を見ると、95%近くがスタチン、約90%が抗血小板薬、7割強がレニン・アンジオテンシン系阻害薬、6割強がβ遮断薬を服用していた。
29カ月(中央値)の観察期間を通じ、両群とも90.3%が試験薬の服用継続が可能だった。
その結果、1次評価項目である「CV死亡、心筋梗塞(MI)、脳梗塞、虚血症状解消のための冠血行再建」の、コルヒチン群(4.2%)における対プラセボ群(5.7%)ハザード比(HR)は0.69(95%信頼区間[CI]:0.57−0.83)となった。このコルヒチン群における1次評価項目抑制は、ACS既往、血行再建術既往(84%)の有無にかかわらず認められた。
また上記から血行再建を除いた「CV死亡、MI、脳梗塞」のみで比較しても、コルヒチン群におけるHRは0.72(0.57−0.92)と有意に低値となっていた。MIのみで比較しても同様である(HR:0.70、0.53−0.93)。
なおコルヒチン群では、CV死亡は減少傾向を認めたものの(0.7% vs. 0.9%、HR:0.80、 0.44−1.44)、総死亡は逆に、多い傾向にあった(2.6% vs. 2.2%、HR:1.26、0.86−1.71)。
有害事象は、発癌、感染症入院、消化器症状による入院とも、両群間に差はなかった。加えて、スタチンとの相互作用による筋障害増加が懸念されていたが、発生率は両群とも0.1%のみだった。
ディスカッションでは、ACS既往例がこれだけ含まれる(高リスク例を対象とした)本データを、冠動脈イベント既往のない安定冠動脈疾患例に当てはめ得るのかとの疑問が出された。しかしNidorf氏は、プラセボ群のイベント発生率を見る限り、決して高リスク患者とは言えないと反論していた。なお、コルヒチン群における総死亡、非CV死亡の増加傾向についての議論はなかった。
本試験は、研究者主導試験であり、豪州政府をメインに、豪州、オランダの民間企業6社などから資金提供を受けて行われた。また報告と同時に、NEJM誌にオンライン公開された。