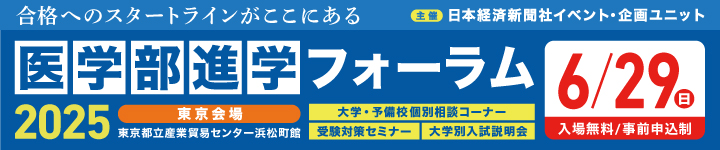お知らせ
■NEWS 【欧州心臓病学会(ESC)】スタチン服用高TG例に対するEPA製剤のプラーク退縮作用が証明される:EVAPORATE試験

2018年の米国心臓協会(AHA)学術集会で報告されたREDUCE-IT試験により、高用量イコサペント酸エチル(EPA)製剤は、スタチン服用下の高トリグリセライド(TG)血症例の心血管系(CV)イベントを抑制した初のTG低下薬となった。そしてその作用機序を探るべく、並行して行われていたランダム化試験“EVAPORATE”の最終結果が、本学会で発表され、高用量EPA製剤によるプラーク退縮作用が確認された。ランドキスト研究所(米国)のMatthew Budoff氏が報告した。
EVAPORATE試験の対象は、スタチン服用下でTG「135~499mg/dL」(REDUCE-IT試験と同一)、かつCT血管造影にて20%以上の狭窄を認めた80例である。冠動脈バイパス術既往例、あるいは直近6カ月に心筋梗塞、脳卒中、生死にかかわる不整脈、いずれかの既往を有する例は除外されている。

平均年齢は57.4歳、男性が54.4%を占め、アジア人も54.4%含まれていた。合併症は高血圧が76.5%、糖尿病が69.1%だった。また54.4%がアスピリンを服用していた。
これら80例は、EPA製剤2g×2/日群とプラセボ群にランダム化され、18カ月、二重盲検法で観察された。
その結果、1次評価項目である「低吸収プラーク」(不安定プラーク)の体積は、プラセボ群で109%増加したのに対し、EPA製剤群では17%の退縮が認められた(P=0.0061)。また「プラーク総体積」もプラセボ群で11%増加したのに対し、EPA製剤群では9%減少していた(P=0.0019)。
本試験は昨年のAHA学術集会にて、9カ月観察の中間解析が報告されている。その時点では、「プラーク総体積」こそEPA製剤群でプラセボ群に比べ有意に低値となっていたものの、1次評価項目である「低吸収プラーク」体積には有意差を認めなかった。しかしながらBudoff氏は「EPA製剤は比較的早期からプラーク進展抑制作用を示す」と述べ、本年5月の心血管造影・インターベンション学会(SCAI)で報告されたREDUCE-IT試験事前設定追加解析(REDUCE-IT REVASC)において、EPA製剤群における冠血行再建術リスクが、試験開始11カ月後にはプラセボ群に比べ有意に低くなっていたのとよく一致すると評価した。
本試験は研究者発案によるものであり、Amarin Pharma, Incの資金提供を受けて行われた。また報告と同時に、Eur Heart J誌にオンライン掲載された。