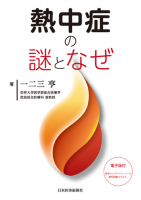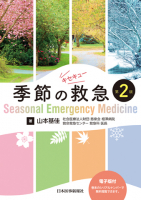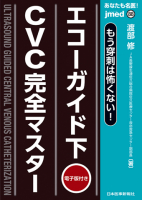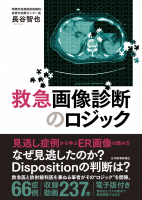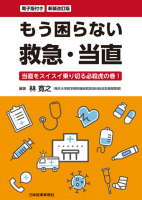お知らせ
めまい[私の治療]
▶緊急時の処置
症状の強い場合は静脈路を確保。
一手目 :ラクテック®注(L-乳酸ナトリウムリンゲル液),またはソリタ®-T3号輸液(維持液)1回500mL(点滴静注)
二手目 :〈心疾患の既往のある場合,処方変更〉5%ブドウ糖液250mL(点滴静注)
三手目 :〈悪心・嘔吐の強い場合,一手目あるいは二手目に追加〉プリンペラン®注10mg(メトクロプラミド)2~3アンプルを混注(持続静注),追加で1アンプルの静注も可
四手目 :〈めまいの強い場合,一手目,二手目あるいは三手目に追加〉アタラックス®-P25mg/mL注(ヒドロキシジン塩酸塩)1回1アンプル(筋注もしくは静注),またはセルシン®注(ジアゼパム)1回5mg(筋注)
▶検査および鑑別診断のポイント
【血液検査・心電図検査】
貧血や不整脈などの評価(上述)。
【鑑別診断・画像検査】
〈回転性〉
90%は末梢性,10%が中枢性。上述の【重症度の判定】①~④のほか,⑤初発の回転性めまい,⑥持続時間が長い(数分~数時間以上),⑦安静で軽快しない,⑧随伴神経症候,および⑨周期性に嘔吐を繰り返す場合,は中枢性めまいを考え,頭部CTの後拡散強調画像を含めた頭部MRI/MRAを行う。中枢性めまいとして,脳血管障害,前庭性片頭痛,神経血管圧迫症候群,緊張型頭痛に伴うめまい,前庭性てんかんなどがあり,末梢性めまいとしてBPPV,メニエール病,突発性難聴,前庭神経炎がある。
〈非回転性〉
回転性,失神性の両方が含まれる。初発の場合は積極的な検索を要する。まず心血管疾患あるいは出血性疾患を,次に中枢神経疾患を考える。頭部画像診断は積極的に行う。緊張型頭痛によるめまい,耳鼻科的疾患,陳旧性脳血管障害,前庭性片頭痛,頸椎症,薬剤性,神経症などがある。
〈失神性〉
血圧が低く,多くは血管迷走神経反射によるものであるが,心血管性疾患や出血性疾患など緊急度の高いものも含まれるので,注意する。
▶落とし穴・禁忌事項
頭部MRI(特に拡散強調画像)による脳幹・小脳病変の診断については,約10%は発症2日を経ても病巣が描出されないことに注意する。
近年,中枢性めまいの鑑別にHINTS(plus)が有効とされるが,患者,特に高齢者には過酷な検査であり,かつその適切な評価には熟練を要する。上述の【神経学的所見】を手がかりに中枢性めまいを診断するほうが効率的である。
▶その後の対応
中枢性は入院加療し,末梢性でも症状の強い例や遷延例,原因のはっきりしない症例では入院が必要である。
【中枢性めまい】
入院の上,専門医に相談する。
【末梢性めまい】
以下の処置の後,耳鼻咽喉科専門医に相談する。症状が遷延あるいは重篤な場合,難聴・耳鳴を伴う場合は入院とする。救急外来で症状が改善すれば原則として帰宅,翌日に耳鼻咽喉科受診を指示する。
〈迷路・内耳循環改善の目的で〉
一手目 :アタラックス®-P注(ヒドロキシジン塩酸塩)1回1~2アンプル(静注)(または生理食塩水50~100 mLと混合し点滴静注)
二手目 :〈一手目に追加〉ソリタ®-T3号輸液(維持液)200 mL+アデホス®-Lコーワ注40mg(アデノシン三リン酸二ナトリウム)1アンプル,メチコバール®注500μg(メコバラミン)1アンプルを1~2時間かけて点滴静注(併用)
三手目 :〈内服薬に変更〉症状が改善し帰宅可能な場合は以下を処方し,翌日耳鼻咽喉科を受診するよう指示。メリスロン®6mg錠(ベタヒスチン)またはセファドール®25mg錠(ジフェニドール)1回2錠1日3回(毎食後),アデホス®コーワ60mg錠(アデノシン三リン酸二ナトリウム)1回1錠1日3回(毎食後),メチコバール®500μg錠(メコバラミン)1回1錠1日3回(毎食後)併用
〈BPPVの場合〉
浮遊耳石置換法で症状を改善させることが可能(手技の詳細は成書を参照)。
一手目 :①後半規管型BPPV:Epley法,Semont法,②外側半規管型BPPV:Lempert法,Gufoni法
二手目 :〈非特異的理学療法として自宅でも行える方法〉③ Brandt-Daroff法
【参考資料】
▶ 室伏利久:めまいの診かた, 治しかた. 中外医学社, 2016, p55-65.
▶ 日本めまい平衡医学会診断基準化委員会:Equilibrium Res. 2009;68(4):218-25.
武田英孝(山王メディカルセンター脳神経内科,国際医療福祉大学臨床医学研究センター教授)