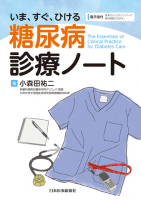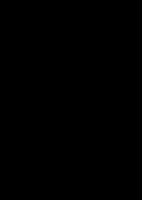お知らせ
■NEWS 【米国心臓協会(AHA)】SGLT2阻害薬による転帰改善作用を「絶対リスク差」で評価すると?:SMART-Cメタ解析

SGLT2阻害薬は今や血糖降下薬の枠を超え、さまざまな疾患に対する転帰改善作用が注目されている。11月5日からシカゴ(米国)で開催された米国心臓協会(AHA)学術集会では、それら有用性を検討したランダム化比較試験(RCT)をメタ解析した“SMART-C”研究が報告された。直前4日に論文が出されたEMPA-KIDNEY試験も含まれている。David Preiss氏(オックスフォード大学、英国)の報告を紹介するとともに、治療効率も検討したい。
メタ解析の対象となったのは、SGLT2阻害薬の有用性をプラセボと比較し、かつ各群500名以上を6カ月以上観察した二重盲検試験である。

対象疾患別に「心血管系(CV)高リスク2型糖尿病(DM)」(4試験、4万2568例)と「心不全(HF)(±DM)」(5試験、2万1947例)、「慢性腎臓病(CKD)(±DM)」(4試験、2万5898例)の3グループに分けられた。
まず「CV死亡・HF入院」は、上記3グループすべてで、SGLT2阻害薬群における有意なリスク低下が観察された。「CV死亡」のみで検討しても同様だった。
ただし「DM非合併」例のみで検討すると、「HF例」ではSGLT2阻害薬で「CV死亡・HF入院」リスクは有意に減少していた一方、「CKD例」ではサンプル数が十分でないこともあり、減少傾向にとどまった。
本メタ解析の特徴は、「絶対リスク減少幅」も算出している点である。
SGLT2阻害薬による上記「CV死亡・HF入院」抑制作用を相対リスクで評価すると、「CV高リスク2型DM例」ではプラセボ群に比べ20%の有意低値だった。一方、これを絶対リスクで評価すると減少幅は「5/1000例・年」であり、1年間の治療必要者数(NNT)を算出すると「200例」となる。
同様に「腎疾患進展」の絶対リスク減少幅は2/1000例・年(1年間NNT:500例)、「急性腎障害」も1/1000例・年(同1000例)だった。
一方「HF例」における「CV死亡・HF入院」絶対リスク減少幅は、「DM合併」ならば34/1000例・年(1年間NNT:30例)、「DM非合併」でも22/1000例・年(同46例)だった。
また「腎疾患進展」の減少幅は「DM合併」で6/1000例・年(同167例)、「DM非合併」は2/1000例・年(同500例)、「急性腎障害」もそれぞれ5(同200例)と6/1000例・年(同167例)だった。
「CKD例」では「腎疾患進展」に対する抑制が著明で、「DM合併」における減少幅は11/1000例・年(1年間NNT:91例)、「DM非合併」で15/1000例・年(同67例)だった。「急性腎障害」減少幅も、それぞれ4(同250例)と5/1000例・年(同200例)、「CV死亡・HF入院」は11(同91例)と2/1000例・年(同500例)だった。ただしDM非合併CKD例は、先述の通りサンプル数が少ない点に留意する必要があるという。
なお指定討論者のNaveed Sattar氏(グラスゴー大学、英国)は、SGLT2阻害薬によるこのような有用性の機序として「血行動態ストレス(hemodynamic stress)減少」と、「細胞過栄養(cellular overnutrition)改善」の可能性を指摘していた。
本メタ解析はUK Medical Research CouncilとKidney Research UKの資金提供を受けた。製薬会社からの資金提供はない。
また発表と同時に、Lancet誌ウェブサイトで論文が公開されている。