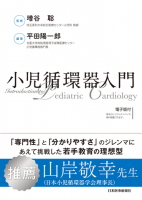お知らせ
川崎病(冠動脈病変)[私の治療]

川崎病は4歳以下の乳幼児に好発する急性熱性疾患で,その主体は全身性の血管炎である。6つの主要症状(発熱,眼球結膜充血,口唇・口腔所見,発疹,四肢末端の変化,非化膿性頸部リンパ節腫脹)により臨床診断を行う。免疫グロブリン静注を中心とした抗炎症療法を行うが,後遺症として冠動脈瘤を残すことがあり,血栓・狭窄・閉塞による急性冠症候群の治療や予防などのため薬物治療が行われる。
▶診断のポイント
急性期の診断には,低侵襲かつ繰り返し行える心臓超音波検査が有用である。各冠動脈枝の血管径のみならず,血管壁の輝度亢進や内腔の血栓形成などがないか,注意深く評価する。性別・体格を考慮した冠動脈内径のZスコア1)を算出し,Zスコアが①2以上2.5未満を拡大,②2.5以上5未満,または実測径3mm以上4mm未満を小瘤,③5以上10未満,または実測径4mm以上8mm未満を中等瘤,④10以上,または実測径8mm以上を巨大瘤,と定義する。遠隔期の評価には心臓カテーテル,造影CT,MRIによる冠動脈画像検査が有用である。成人期では,冠動脈瘤の重症度基準は確立していない。

急性冠症候群の診断には心電図(ST変化),心臓超音波(局所心筋壁運動異常),血液検査(心筋逸脱酵素など)を組み合わせて評価する。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
冠動脈拡大あるいは小瘤の場合,血栓性閉塞は稀であるが,退縮するまでアスピリンを使用することが多い。中等瘤以上の場合はアスピリンを継続し,時に他の抗血小板薬を併用することもある。実測径6mmを超える瘤の場合は,ワルファリンによる抗凝固療法の併用が望ましい2)。アスピリンによる胃潰瘍は,小児では稀である。ワルファリンはPT-INR 2.0~2.5を目標に投与量を調整する。ワルファリンの抗凝固作用は,食事や薬品の影響を受けやすく,発熱,胃腸炎罹患,食事摂取不良時には増強するため,出血性合併症に注意が必要である。
その他の薬物治療として3),冠動脈瘤が残存し狭窄性病変を有する症例に対し,病態に応じてβ遮断薬,カルシウム拮抗薬,硝酸薬などを投与する。予後の改善を期待して,アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬,アンジオテンシンII受容体拮抗薬(ARB),スタチン製剤が使用されることもあるが,いずれもエビデンスレベルは低く保険適用外である。
心筋梗塞の急性期には,発症12時間以内に再灌流療法の実施をめざす。患者の体格や施設の状況が許せば経皮的冠動脈形成術が望ましいが,困難な場合には血栓溶解療法を行う。

残り1,175文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する