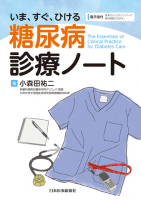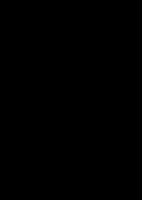お知らせ
【文献 pick up】デノスマブでBP剤に比べ2型糖尿病発症リスク低?―大規模観察研究/BMJ
糖尿病(DM)は骨粗鬆症の「臨床的危険因子」である(「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版」p15)。では骨粗鬆症治療薬が糖代謝に及ぼす影響はどうか。
米国では唯一の第一選択とされているビスホスホネート(BP)製剤(「米国内科学会2023年ガイドライン」p4)は、ランダム化比較試験(RCT)メタ解析の結果、DM発症に対する抑制傾向が明らかになっている(相対リスク:0.93、95%信頼区間[CI]:0.74−1.18)。
一方、同ガイドラインでは「ビスホスホネート禁忌・不耐の閉経後女性」にのみ推奨されているデノスマブでは、DPP-4血中濃度を低下させ、GLP-1濃度を上げるとの臨床データが報告されており、RCTではプラセボに比べ2型DM発症を抑制する傾向を認めた。
ではこれら2剤のDM発症に与えるリスクに差はあるか。この点を検討した観察研究が4月18日、BMJ誌に掲載された。著者は中南大学(中国)のHouchen Lyu氏ら(責任著者は米国ハーバード大学のDaniel H Solomon氏)。
2型DM高リスク例に限れば、デノスマブによるDM発症抑制作用が高い可能性が示された。概要を紹介したい。
解析対象となったのは、1995〜2021年に経口ビスホスホネート製剤服用、またはデノスマブを開始(新規・切替)した、45歳以上でDM診断歴のなかった21万1831例中、傾向スコアでマッチできた2万5339例(うちデノスマブ4301例)である。英国プライマリケアデータベース“IMRD”から抽出した。
その結果、追跡開始後5年間の2型DM発症率はデノスマブ群4.3/1000例・年、経口BP製剤群8.3/1000例・年となり、デノスマブ群におけるハザード比(HR)は0.68の有意低値となった(95%CI:0.52−0.89)。
ただし細かく見ると、DM予備群(prediabetes、全体の22.2%)ではデノスマブ群における2型DM発症HRが0.54(95%CI:0.35-0.82)の有意低値だった一方、非予備群では0.92(95%CI:0.65-1.32)とリスク減少幅は縮小し、有意差にも至らなかった。なお、交互作用P値は0.05である。
本解析への資金提供の有無は記されていない。また著者らは製薬会社からの資金提供を受けていないとされる。