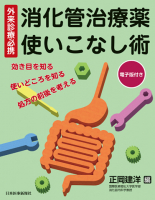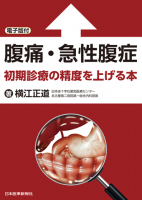お知らせ
直腸粘膜脱症候群[私の治療]

「solitary rectal ulcer syndrome」と呼ばれることもあるが,後述するように,必ずしもすべての患者で潰瘍性病変を伴うわけではないため,むしろ,病態が含まれる「直腸粘膜脱症候群」という疾患名が適切と思われる。先天性と後天性があるが,後天性は高齢者に多く,肛門括約筋の弛緩,機能障害,また骨盤を支える肛門挙筋の機能低下が,直腸の脱出に関与すると考えられている。他の要因として,直腸S状結腸の過長,直腸重積,深く下降した骨盤底,仙骨弯曲の不足などが指摘されている。実際,直腸括約筋協調運動障害(dyssynergia)が2/3の患者で認められたという報告がある。慢性の病態であることから,治療の有無にかかわらず,症状が消失することは少なく,QOLが障害され続けるとされている。
▶診断のポイント
出血,テネスムス,排便時のいきみといった臨床症状を訴える患者において,矛盾のない内視鏡所見が得られた場合に診断される。一方で,無症状で,内視鏡検査の際に病変が指摘されることも稀ではない。また,生検組織の病理学的所見としては,粘膜固有層の平滑筋の増生を伴う線維筋症(fibromuscular obliteration)が特徴的である。肉眼分類(内視鏡所見)としては,①平坦型,②隆起型,③潰瘍型,④深在囊胞性大腸炎型,が提唱されている。病変部位としては,通常,直腸前壁の肛門縁から10cm以内であることが多い。直腸脱の評価としては,怒責排便検査,デフェコグラフィー,直腸肛門角の角度の計測や,直腸肛門内圧検査による,肛門括約筋の機能低下の評価も行われる。

鑑別診断としては,直腸の腫瘍性病変が挙げられるが,本疾患において特異的な肉眼所見はないため,生検組織の病理学的検索は鑑別診断という観点からも重要と考えられる。また,炎症性腸疾患のほかに,鑑別において考慮される感染症としては,アメーバ赤痢,クラミジア直腸炎,単純ヘルペスウイルス,サイトメガロウイルス,梅毒などが挙げられる。

残り824文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する