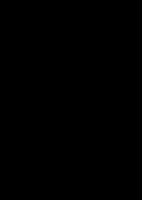お知らせ
学会レポート─2023年欧州糖尿病学会(EASD)[J-CLEAR通信(164)]

2023年10月2日から5日間、ドイツ・ハンブルクで欧州糖尿病学会(EASD)第59回学術集会が、現地・オンラインのハイブリッドで開催された。参加者は合わせて1万1000人超。10年以上前からハイブリッド開催を続けてきた本学会だが、本年のバーチャルサイトは例年よりも内容・使い勝手とも改善されていた。薬効とは関係のない話題を中心に紹介したい(10月のウェブ掲載速報を整理・加筆)。
TOPIC 1
低用量放射線被ばくで糖尿病発症リスク上昇の可能性─日本からの報告
放射線被ばくは低用量でも糖尿病(DM)発症リスクを上昇させる可能性が、原子力発電所災害時作業員を対象とした観察研究の結果、明らかになった。Huan Hu氏(労働安全衛生総合研究所、日本)が報告した。

【対象】
解析対象となったのは2011年3〜12月に東京電力福島第一原子力発電所で作業にあたった1万9812例中、観察研究の呼びかけに応じ、かつ検診データがそろっていた男性作業員5326例である(女性11例は除外)。
平均年齢は45歳前後、60%弱に脂質異常症、35%前後に高血圧を認めた。
【方法】
これら5326例のデータセットを用い、ホールボディ・カウンタ評価による放射線内部被ばく量と、その後10年間の定期検診におけるDM発症の関係を後方視的に調べた。
「DM」の定義は「DM診断」ないし「空腹時血糖値≧126mg/dL、またはHbA1c≧6.5%」とした。
【結果】
その結果、5年間で392例に新規DM発症を認めた(7.8%)。
そこで「内部被ばく量」と「DM発症リスク」の関係を以下のように検討した。
すなわち全体を「0−4」mSv(2621例)、「5−9」mSv(732例)、「10−19」mSv(823例)、「20−49」mSv(787例)、「≧50」mSv(363例)の5群にわけ、「0−4」mSv群を基準としたDM発症ハザード比(HR)を算出する。
その結果「10−19」mSv群でもHRは1.47、「20−49」mSv群では1.33の有意高値となっていた(95%信頼区間の数字は示されず)。一方、意外にも最も被ばく量の多い「≧50」mSv群におけるHRは0.98だった。
この結果は、観察開始直後の3年間にDMを発症した105例を除外した解析でも同様だった。
なおHR算出にあたっては、年齢やBMI、正社員/派遣の別、教育レベル、身体活動、アルコール摂取、脂質異常症、高血圧による影響を補正している。
【考察】
内部被ばく量「≧50」mSv群でDM発症リスク上昇が認められなかった理由としてHu氏は「サンプル数が少ない」点を挙げ、より長期間観察すればこの群でも発症リスクは上昇するのではないかとの見方を示した(観察は今後も継続)。
本研究は、厚生労働省・労災疾病臨床研究事業「放射線業務従事者の健康影響に関する疫学研究」の一環として実施された。
TOPIC 2
GIP/GLP-1デュアルアゴニストで除脂肪筋肉量減少の可能性─RCT“SURPASS-3”MRIサブスタディ
GIP/GLP-1デュアルアゴニストであるチルゼパチドはGLP-1受容体アゴニストを上回る減量作用が、正常体重を超える2型糖尿病(DM)を対象とした大規模ランダム化比較試験(RCT)“SURPASS-2”で示されている。そのような減量にあたり懸念されるのが、体組成への悪影響(筋肉量減少)である。今回、RCTサブスタディの結果として、52週間のチルゼパチド使用による除脂肪筋肉量減少の可能性が示された。Jennifer Linge氏(リンシェーピング大学、スウェーデン)が報告した。
【対象】
今回解析対象となったのは、SURPASS-3 MRIスタディに参加した「BMI 25~45kg/m2で直近3カ月の体重が安定」し、かつメトホルミン(±SGLT2阻害薬)服用下で血糖管理不良の2型DM 296例である。
平均年齢は56.2歳、HbA1c平均値は8.2%、平均体重は94.4kg、BMI平均は33.5kg/m2だった。
【方法】
これら296例はチルゼパチド5、10、15mg群、あるいはインスリン・デグルデク群にランダム化され、52週間観察された(非盲検)。
全例、試験開始前と開始52週間後にMRIを用いて大腿部の「除脂肪筋肉量」を定量化、「筋肉内脂肪浸潤」の割合も測定した。MRIを用いた除脂肪筋肉量測定は、DXAによる筋肉量推算よりも正確とされる。
【結果】
・体重
血糖降下薬開始52週間後、体重は既報1)の通り、デグルデク群に比べチルゼパチド群で用量依存性に7.8~11.2kg、有意に減少した。
・筋肉への影響
「除脂肪筋肉量」は、デグルデク群で52週間に0.16L増加したのに対し、チルゼパチド群では用量依存性に0.44~0.76Lの減少を認めた(検定結果の提示なし)。
一方「筋肉内脂肪浸潤」率は、デグルデク群で0.03%上昇していたのに対し、チルゼパチド群では用量依存性に0.23~0.44%低下していた(検定なし)。
なおこれらの結果からLinge氏が導いた結論は、「チルゼパチドは筋組成に明らかな悪影響を及ぼすことなく、体重と脂肪を改善する」だった。
本試験はEli Lilly and Companyからの資金提供を受けて実施された。またLinge氏は今回用いられたMRIモダリティを扱うAMRA Medicalの社員でもある。
TOPIC 3
HFrEFに対するSGLT2阻害薬の心保護作用は心外膜脂肪への介入も関与? ─チェコ52例比較
SGLT2阻害薬は心不全例の「心血管系死亡・心不全入院」を抑制するが2)、その機序は必ずしも明らかでない。Milos Mráz氏(臨床実験医学研究所、チェコ)は、SGLT2阻害薬が左室機能低下心不全(HFrEF)例の心外膜脂肪に直接作用し、心保護的に働いている可能性を報告した。
心外膜脂肪は正常であれば心保護的に作用するが、過度に蓄積すると炎症惹起や線維化の促進、あるいは自律神経機能障害などを介してHFrEFを増悪させると考えられている。そのため、心保護治療における新規標的の1つとして注目されている3)。
【対象】
今回解析の対象とされたのは、心移植・補助人工心臓植え込み予定のあるNYHA分類Ⅲ、Ⅳ度のHFrEF 52例である。26例がSGLT2阻害薬を服用、26例は非服用だった。
「服用」群、「非服用」群とも平均年齢は約55歳、BMIは28kg/m2前後だった。また左室駆出率はいずれもおよそ20%、BNP濃度は1200ng/L前後で群間差はなかった。同様に血中hsCRP濃度も5.0mg/L前後で両群同等、脂質代謝にも群間差を認めなかった。
一方、糖尿病(DM)合併例が占める割合は「服用」群は「非服用」群の2倍以上であり(69.2% vs. 30.8%)、HbA1c平均値も有意に高かった(6.9% vs. 6.1%)。
【方法】
これら52例から心外膜脂肪を心移植・デバイス植え込み時に採取し、SGLT2阻害薬「服用」「非服用」群間で比較した。
【結果】
まず遺伝子発現パターンを調べると(トランスクリプトーム解析)、SGLT2阻害薬「服用」群では、心外膜脂肪細胞における「脂肪酸の合成抑制・分解亢進」「炎症抑制」(JAK-STAT系、NF-κB抑制)「細胞老化とアポトーシスの抑制」が示唆された。
一方、心外膜脂肪細胞におけるSOD2発現は、「服用」「非服用」群間で差はなかった。ただし「服用」群ではミトコンドリアサイズの拡大(機能改善)が認められた。なお皮下脂肪ではこの改善を認めなかった。
また免疫反応も「服用」群は「非服用」群に比べ、心外膜脂肪細胞におけるマクロファージとヘルパーT細胞(Th1、Th2)の発現減弱を認めた。一方、皮下脂肪ではこのような差を認めなかった。
さらに「服用」群では、心外膜脂肪細胞におけるジアシルグリセロール減少とエーテル脂質の増加を認めた。
Mráz氏によればこの変化はフェロトーシス(プログラム化細胞死の一種)抑制的に作用するという。
【考察】
これらの結果から同氏は、SGLT2阻害薬は重度HFrEF例の心外膜脂肪における(1)抗炎症、(2)ミトコンドリア機能改善(疑問符付き)、(3)細胞老化・細胞死の抑制─を介し、心保護的に作用している可能性があると結論していた。
Mráz氏に開示すべき利益相反はないという。また本研究は欧州連合からの資金提供を受け、チェコ科学アカデミーからも支援を受けた。
TOPIC 4
CV疾患1次予防2型糖尿病ではQT延長薬で心臓突然死リスク著増の可能性─オランダ大規模症例対象研究
わが国の観察研究は、糖尿病(DM)入院既往例死亡の3割は突然死であり、一般疫学調査の10%前後を大きく上回ると報告している4)。2型DM例ではこの心臓突然死(sudden cardiac arrest:SCA)リスクが、QT延長作用のある抗精神病薬や抗生剤により著明上昇している可能性が、大規模症例対象研究から示された。Peter P. Harms氏(アムステルダム自由大学医療センター、オランダ)が報告した。
【対象】
解析対象は、2型DMをプライマリケアで加療中にSCAをきたした689例と、診察時期、年齢・性別をマッチさせた非SCA 3230例である。SCA例は地域レジストリから抽出、2型DM例はプライマリケア・データベースを参照してピックアップした。
平均年齢は68歳、男性が65%弱を占めた。HbA1c平均値は約6.5%だった。心血管系(CV)疾患既往例の割合は「SCA」群が「非SCA」群より高かったが(40.0 vs. 29.4%)、降圧薬や脂質低下薬の服用率には群間差はなかった。
【方法】
これらSCA群の発生前5年間の診療記録を非SCA群と比較し、心停止のリスク因子を探った(多変量解析)。
【結果】
その結果、SCAと相関する複数の因子が明らかになり、中でもHarms氏が注目したのは「QT延長をきたしうる薬剤」である。非服用例に比べてSCAリスクは「不整脈既往」と同等まで上昇していた(ハザード比[HR]:1.66、95%信頼区間[CI]:1.20−2.31)。
ただし細かく見ると、QT延長薬に伴うSCAリスクの有意上昇を認めたのは、CV疾患1次予防例のみだった。すなわち抗精神病薬に伴うSCAのHRは2.87(95%CI:1.95−4.22)、抗生剤でも1.66(95%CI:1.15−2.39)の有意高値となっていた。
なお上記薬剤以外でHarms氏が強調したSCAリスク因子は、CV疾患1次予防2型DM例における「空腹時血糖値<81mg/dL」である。「81–<114mg/dL」に比べHRは2.50(95%CI:1.15−5.44)と有意に高かった。
本研究に開示すべき利益相反はないとのことである。
TOPIC 5
閉経前女性のHbA1c正常値上限は引き下げが必要? ─英国大規模観察研究
現在、HbA1cの正常値上限は「6.5%」が一般的だが、若年女性に限っては少し引き下げるべきではないだろうか─。このように結論する観察研究が報告された。背景にあるのは、女性では2型糖尿病(DM)合併に伴う死亡の相対リスク上昇幅が、男性よりも有意に大きいという事実である5)。この理由として報告者であるMichael Stedman氏(RES Consortium、英国)らは、女性の若年時のDMが見逃され、血糖管理が不十分だった可能性を指摘している。
【対象と方法】
今回Stedman氏らが解析対象としたのは、英国の複数レジストリに2012~19年の間に登録された、HbA1c値「4.0−<6.7%」だった健常者14万6907例である。年齢中央値は48歳だった。対象者を男女別にわけ(女性:54.5%)、年齢ごとにHbA1c値を比較した。
【結果】
その結果、男女ともHbA1c値は年齢が上がるに従い上昇した。ただし50歳に至るまでは一貫して、男性に比べて女性で著明低値を認めた。
すなわち「50歳未満」に限れば、女性の平均HbA1c値は男性よりも2.3%低く、10歳若年の男性と同等だった。一方「50歳以上」では、このようなHbA1cの著明な男女差を認めることはなかった。
また女性における「HbA1c≧6.5%」(DM)の割合は、「50歳未満」では男性の約5割のみだったが、「50歳以上」ならば約8割まで増えていた。
【考察】
Stedman氏らは、50歳未満でのみ特異的に男性と比較してHbA1c値低値が著明な理由として、「月経」を挙げた。糖化ヘモグロビン入れ替えの影響でHbA1c値が実際よりも低く出ている可能性があるという。
そのため50歳未満女性ではDM発症が見逃され、ひいては死亡リスクが上昇しているのではないか─。こう推論した上でStedman氏らは、閉経前女性の至適HbA1c値を引き下げるべきではないかと問いかけた。
著者らに開示すべき利益相反はないとのことだ。また、本研究に対する資金提供の有無は示されなかった。
本研究は報告と同時に、Diabetes Therapy誌ウェブサイトで公開された6)。なお同様の観察研究はサウジアラビアからも報告されている7)。
TOPIC 6
1型糖尿病例では心筋梗塞後転帰の経年的改善を認めず─スウェーデン大規模観察研究
2型糖尿病(DM)例では過去15年間に、心筋梗塞後の生存率が経年的に改善していたのに対し、1型DMではそのような改善が認められないことが明らかになった。Linn Glynn氏(カロリンスカ研究所、スウェーデン)が報告した。1型、2型DM間でこの差が生じた原因は明らかでないという。
【対象と方法】
今回解析対象となったのは、スウェーデン在住で2006~10年の間に急性心筋梗塞をきたし、DM合併の有無が明らかだった29万4018例である。このうち24万3170例にはDM診断歴がなく、2527例に1型DM、4万8321例に2型DMの診断歴があった。
これら3群間で心筋梗塞後死亡率の経年的変化を比較した。
平均年齢は「1型DM」群が62.0歳で、「2型DM」群の75.0歳、「非DM」群の73.2歳に比べて若い傾向にあった。女性の割合は「1型DM」群が43.6%で、「2型DM」群(38.1%)や「非DM」群(38.4%)に比べて高い傾向を認めた。
一方、DM罹患期間は「2型DM」群が12.9年だったのに対し、「1型DM」群は42.9年だった。HbA1c平均値は「2型DM」群の7.3%に対して「1型DM」群は8.4%だった(検定なし)。
心筋梗塞の内訳は、「1型DM」群と「2型DM」群ではST上昇型(STEMI)がともに約30%だったのに対し、「非DM」群では38%だった。
【結果】
心筋梗塞発症後「30日間死亡率」の経年的推移を見ると、「06~08」年から「18~20」年にかけて「非DM」群では0.48%の低下、「2型DM」群でも0.33%低下していたのに対し、「1型DM」群では有意な低下は認められなかった(0.18%の低下傾向)。
「1年間死亡率」の経年的変化も同様で、「非DM」群の0.65%、「2型DM」群の0.50%の有意低下と対照的に、「1型DM」群では0.17%の低下傾向(NS)のみだった。
「心血管系死亡」「重篤心血管系イベント」の経年的推移を比較しても同様の結果だった。
【考察】
質疑は1型DMのみ心筋梗塞後転帰の経年的改善が認められなかった原因に集中した。
Glynn氏によれば、心筋梗塞発症後のスタチン、アスピリン服用率は「1型DM」群と「2型DM」群の間に差はなく、また「非DM」群に比べると高かったという。
さらにSGLT2阻害薬服用率は「18~20」年時点でも「2型DM」群で約6%、「1型DM」群で2%強のみで、この差が死亡率改善の差につながったとは考えられないと同氏は述べた。事実、SGLT2阻害薬の臨床応用前から「2型DM」群の死亡率減少は始まっていたという。
この点はGLP-1RAに関しても同様とのことだ。
また脂質についてはLDL-Cの管理目標値達成率に「1型DM」群と「2型DM」群の間で差はなかった。
しかしトリグリセライド、HDL-Cについてのデータは今回提示されず、フロアからは「1型DM」群と「2型DM」群の間ではそれらの管理状況に差があったのではないかとの指摘があった。
Glynn氏自身は「1型DM」群の「HbA1c高値」、またそこから想起される相対的に大きな血糖変動が悪影響を及ぼしていると考えているようだった。
Glynn氏に開示すべき利益相反はないという。研究に対する資金提供の有無には言及がなかった。
【文献】
1) Gastaldelli A, et al:Lancet Diabetes Endocrinol. 2022;10(6):393-406.
2) Vaduganathan M, et al:Lancet. 2022;400(10354): 757-67.
3) Iacobellis G:Nat Rev Cardiol. 2022;19(9):593-606.
4) 紀田康雄, 他:糖尿病. 1993;36(4):277-83.
5) Prospective Studies Collaboration and Asia Pacific Cohort Studies Collaboration:Lancet Diabetes Endocrinol. 2018;6(7):538-46.
6) Holland D, et al:Diabetes Ther. 2024;15(1):99-110. doi:10.1007/s13300-023-01482-6
7) Alghamdi AS, et al:Curr Diabetes Rev. 2021;17(3): 365-72.