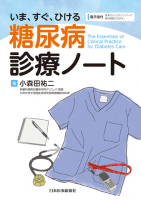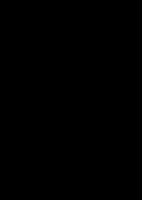お知らせ
【文献 pick up】週1回GLP-1-RA製剤でCKD合併2型DM例の心腎転帰改善:大規模RCT “FLOW”/NEJM誌
慢性腎臓病(CKD)を合併した2型糖尿病(DM)に対して、GLP-1受容体作動薬(RA)も心腎保護作用を有することが、大規模ランダム化比較試験(RCT)"FLOW"の結果、明らかになった。ニュー・サウス・ウェールズ大学(豪州)のVlado Perkovic氏らが5月24日、New England Journal of Medicine誌で報告した。今後はSGLT2阻害薬へ相乗/相加効果の有無、同薬との使い分けなどが検討課題となりそうだ。
【対象】
FLOW試験の対象は日本を含む28カ国から登録された、アルブミン尿陽性のCKDを合併した、2型DM3533例である。

eGFR「50~75」mL/分/1.73m2であればアルブミン/クレアチニン比「300~5000」mg/g、「25~50」mL/分/1.73m2ならば「100~5000」mg/g例が組み入れられた。原則として忍容最大用量のレニン・アンジオテンシン系阻害薬服用が必須だったが、非忍容例も参加可能だった(約5%)。平均年齢は66.6歳、女性は30.3%のみだった。試験開始時のHbA1c平均値は7.8%、eGFR平均値は47.0 mL/分/1.73m2だった。また肥満/過体重例が多かったようで、平均体重は89.6 kg、BMI平均値は32.0 kg/m2である。
心腎保護薬としては、約95%がRAS-iを服用し、スタチンも約80%で用いられていた。一方、SGLT2阻害薬服用率は15.6%のみだった。
【方法】
これら3533例は、GLP-1-RA(週1セマグルチド1.0mg目標)群とプラセボ群にランダム化され、「心腎イベント」(1次評価項目)発生リスクが二重盲検法で比較された。心腎イベントの内訳は「腎不全」「28日以上持続する50%以上のeGFR低下」「腎関連死亡」「心血管系(CV)死亡」―である。
【結果】
・早期中止
当初イベント数「854」発生時の終了を予定していたが、「570」発生時点で早期中止基準を満たしたため、終了となった。観察期間中央値は3.4年である。
・1次評価項目
その結果GLP-1-RA群は、プラセボ群に対して心腎イベントのハザード比(HR)が0.76の有意低値となっていた(95%信頼区間[CI]:0.66-0.88)。発生率を比較すると「5.8 vs. 7.5」/100人年である(NNT:59/年)。両群の発生率曲線の乖離は、開始後18カ月から著明に大きくなった。しかしその傾向は持続せず、42カ月後以降、両群の発生率曲線はほぼ並行(または差が縮小傾向)となった。
なお少数例(n=550)での検討だが、SGLT2阻害薬「服用」例では、GLP-1-RA群におけるHRは1.07(95%CI:0.69-1.67)だった(交互作用P値なし。ただし「考察」に「明確なバラツキはなし」との記載)。
・腎機能(2次評価項目)
2次評価項目(階層順評価)の筆頭である「eGFR低下速度」も、GLP-1-RA群で有意に低かった(-2.19 vs. -3.36 mL/分/1.73m2/年)。なおGLP-1-RA群では開始直後のeGFRの低下幅がプラセボ群よりも大きく、その後、回復してeGFRがプラセボ群を上回る、いわゆる「イニシャル・ディップ」が認められた。
・CVイベント/総死亡(2次評価項目)
同様に「CV死亡・心筋梗塞・脳卒中」初発リスクも、GLP-1-RA群で有意に低くなっていた(HR:0.82、95%CI:0.68-0.98)。総死亡も同様である(HR:0.80、95%CI:0.67-0.95)。
・安全性
有害事象による使用中止率は、GLP-1-RA群で13.2%、プラセボ群が11.9%だった。
本試験はNovo Nordiskから資金提供を受けて実施された。同社は統計解析も実施し(第三者が検証。論文著者が触れ得たのは解析後データ)、論文草稿に対するレビュー/アドバイスも実施した。ただし内容・出版に関する最終決定権は原著者たちに留保されていた。