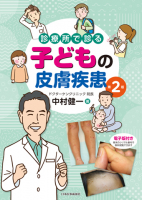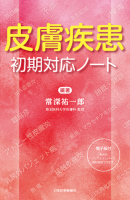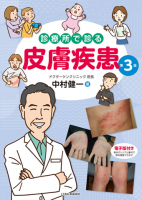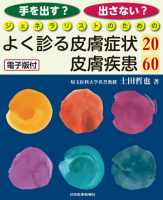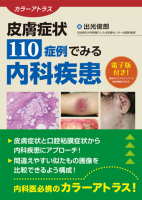お知らせ
蕁麻疹[私の治療]
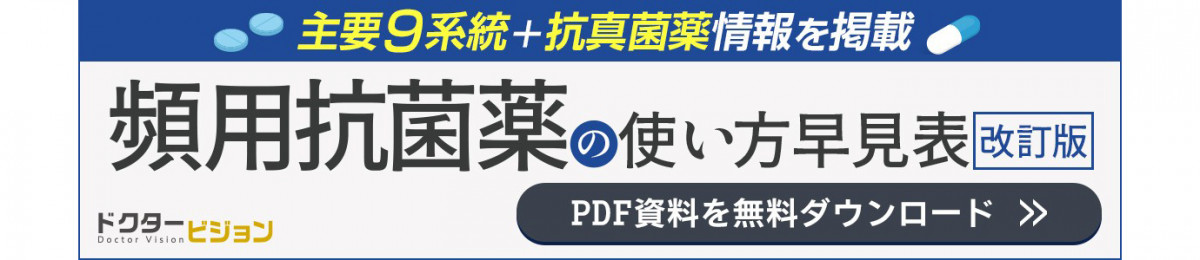
蕁麻疹は膨疹,つまり紅斑を伴う一過性,限局性の浮腫が病的に出没する疾患であり,多くはかゆみを伴う。特定刺激ないし負荷により皮疹を誘発することができる刺激誘発型の蕁麻疹と,個々の皮疹に関する直接的原因ないし誘因なく自発的に膨疹が出現する特発性の蕁麻疹に分類される。
▶診断のポイント
かゆみを伴う膨疹が24時間以内に出没することが確認できれば,ほぼ蕁麻疹と考えてよい。

▶私の治療方針・処方の組み立て方
皮疹を誘発可能な刺激誘発型の蕁麻疹では,皮疹の誘発因子の同定とそれらの因子の回避の指導が治療の中心である。機械的な刺激によって蕁麻疹(いわゆるミミズ腫れ)が出現する機械性蕁麻疹では機械的な刺激を回避すると同時に,ヒスタミンH1受容体拮抗薬(抗ヒスタミン薬)を内服する。アレルゲンの摂取などによって蕁麻疹が出現するアレルギー性の蕁麻疹では,アレルゲンの同定とその除去,回避が重要であり,完全な除去,回避が困難な場合は抗ヒスタミン薬を事前内服,事後内服,場合によっては定期内服することによって症状を軽減させる。
一方で,自発的に皮疹が出現する,つまり直接的な原因のない特発性の蕁麻疹では,薬物療法を継続しつつ病勢の鎮静化を図ることが重要である。特発性の蕁麻疹は発症6週間以内のものを急性蕁麻疹,6週間を超えるものを慢性蕁麻疹と分類し,蕁麻疹の大半は特発性の慢性蕁麻疹である。抗ヒスタミン薬を中心とした薬物療法によって,第一目標は治療により症状が現れない状態を,最終目標は無治療で症状が現れない状態をめざす。
日本皮膚科学会の「蕁麻疹診療ガイドライン2018」1)では,Step 1として非鎮静性第2世代抗ヒスタミン薬通常量を処方し,改善しない場合は適宜他剤への変更,2倍量までの増量または2種類の併用を推奨している。それでも改善しない場合は,Step 2としてStep 1にH2受容体拮抗薬,抗ロイコトリエン薬,トラネキサム酸,漢方薬などの補助的治療薬を追加または変更してもよい,としているが,エビデンスレベルは高くはなく,また一部の薬剤は保険適用の点で注意が必要である。それでも改善しない場合は,Step 3として,Step 1またはStep 1,2に追加または変更して副腎皮質ステロイド,オマリズマブ,シクロスポリンを推奨しているが,オマリズマブ以外は保険適用の点で注意が必要となる。
なお,EAACI/GA2LEN/EuroGuiDerm/APAAACIの国際ガイドライン2)では,まずは第2世代抗ヒスタミン薬を通常量投与して,改善しない場合は必要に応じて抗ヒスタミン薬の増量(4倍量まで)を推奨している(わが国では保険適用上,2倍量までの増量が許容されると考えられる)。それでも改善しない場合は,第2世代抗ヒスタミン薬にオマリズマブの追加を推奨している。さらに改善しない場合は,第2世代抗ヒスタミン薬にシクロスポリンの追加を推奨しているが,わが国では蕁麻疹にシクロスポリンの保険適用はない。

残り735文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する