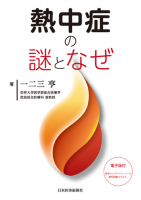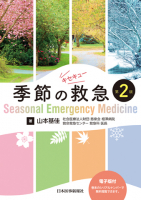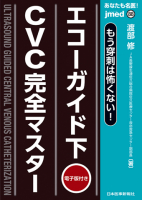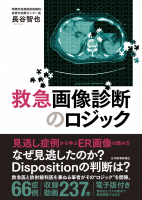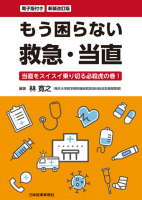お知らせ
高山病[私の治療]
富士山など標高2500m以上の登山や,高地への飛行機移動でしばしばみられる急性高山病と,重症病態である高地脳浮腫および高地肺水腫では,緊急性と重症度が大きく異なる。
重症病態に対しては,高所での限られた医療資源で治療を行いながら,早急に低地に移送することが重要である。
▶病歴聴取のポイント
登山などによって気圧や酸素濃度が低い高地環境に曝された際に,環境変化に適応できず,頭痛,嘔気・嘔吐,疲労・脱力感,めまい,睡眠障害などの症状を呈する状態が急性高山病である。

急性高山病は,通常2500m以上で発症するが,2500m未満でも同様の症状を呈することもある。重症化のリスクは,若年,到達高度,高地への到達速度である。高地脳浮腫は,急性高山病から進行し,頭蓋内圧亢進による精神症状,運動失調,意識障害などを呈する。高地肺水腫は,非心原性肺水腫であり,頻呼吸や呼吸困難,起坐呼吸などを呈する。
高地環境への曝露状況とこれらの症状を聴取することが,最も大切なポイントである。
▶バイタルサイン・身体診察のポイント
【バイタルと意識状態】
- 急性高山病では,バイタルサインの大きな異常を呈さない。
- 高地脳浮腫では,意識障害を呈することがある。
- 高地肺水腫では,頻呼吸を呈する。
【身体診察】
- 高地脳浮腫の症候として,複視,運動失調などを確認する。
- 高地肺水腫では,チアノーゼ,湿性ラ音の聴取などを確認する。パルスオキシメータがあれば,動脈血酸素飽和度のモニタリングをする。

残り1,310文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する