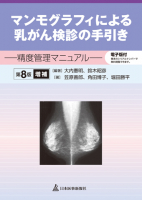お知らせ
前立腺癌に対する小線源治療の適応の現況と注意点
【Q】
わが国で前立腺癌放射線治療に小線源治療が導入されて10年以上が経過していますが,当初,低リスク群への適応であったものが,最近,高リスク群に適応が拡大しています。前立腺癌に対する小線源治療の適応の現況と注意点について,日本におけるパイオニアである国立病院機構東京医療センター・萬 篤憲先生のご教示をお願いします。
【質問者】
幡野和男:東京ベイ先端医療・幕張クリニック院長
【A】
小線源治療の適応が拡大された背景には3つの要素があります。高い線量による中・高リスクの成績の向上が次々と報告されたこと,それを支援する技術が向上し,製品が進化したこと,そして米国のガイドラインにおいて適応が明記されたことです。技術が未熟であった1990年代半ばの米国の報告では,高リスク群に対する小線源単独治療の成績は不良であり,低リスクであるほど良い適応であるという触れ込みで2003年に日本に導入されました。
しかし,2000年代には中・高リスクに対する小線源治療および外照射併用小線源治療の良好な成績が北米から次々と報告されました。その結果をふまえて,米国の小線源治療学会のコンセンサスガイドラインのみならず,National Comprehensive Cancer Network(NCCN)ガイドラインでも,中・高リスクへの小線源治療の適応が明記されました。
小線源治療では前立腺に確実に高線量を1回の処置で投与することが可能であり,さらに外照射併用により外照射単独や小線源単独よりも高い生物学的な線量が投与可能とされています。低・中リスクに対しては内分泌療法を併用しなくても,非常に良好な治療成績が得られています。この10年間,日本国内でも技術が向上し,計画法や新型線源の開発により,被膜外へも十分な照射が可能となりました。
ただし,中間リスクの一部や高リスクに対しては外照射併用が必要と考えられています。リスクが高いほど,内分泌療法の併用も勧められます。また,I-125シード線源のみならず,Ir-192高線量率組織内照射も普及が進み,特に中・高リスクに対して有効なことが示されています。
注意点はいくつかあります。小線源治療は外照射と異なり,手技を含めた技術的習熟度が大変重要であり,泌尿器科医と放射線腫瘍医の良好な連携が必須です。そのため,どの施設でも可能な治療とは言えません。また,投与線量が高いこともあり,尿道の刺激症状を2~3年にわたり繰り返すことがあり,線源の安全管理や再発形式も含めて患者さんへの説明や対応に配慮が必要です。
前立腺肥大症状がもともと強い人の場合には尿道の後遺症が強く出るリスクが高くなります。副作用が強く懸念される場合には,手術や外照射,監視療法など,いろいろな選択肢も十分吟味するべきです。外照射併用の場合には直腸への影響が目立ちやすく,できるだけ高精度な外照射との併用をお勧めします。また,残念ながら治療後に再発してしまった場合の対応も,再発部位の確認や救済治療に関していろいろな選択肢をよく検討する必要があります。