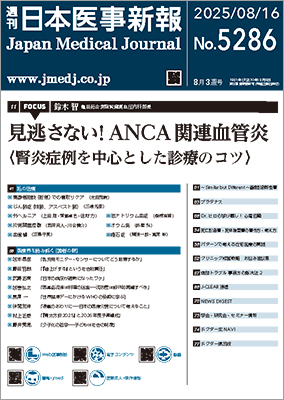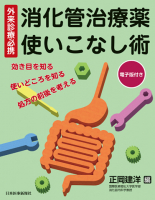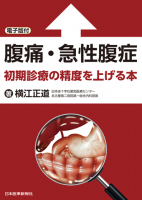お知らせ
直腸MALTリンパ腫の取り扱い

【Q】
直腸MALT(mucosa-associated lymphoid tissue)リンパ腫の治療,特に早期(ステージⅠ~Ⅱ1)の病変について。本疾患に対する標準的な治療や,ガイドラインなどは作成されておらず,症例報告などを参考に治療を行っているのが現状です。最初に行う治療としては除菌療法が一般的だと思いますが,除菌療法も1回で病変が消失する症例もあれば,消失まで数回施行した症例も経験しています。除菌療法は何回まで試みるべきなのか,縮小しない場合は経過観察でよいのか,それともさらなる加療を行うべきなのか,その際にどの治療を優先して行えばよいのかなど,現時点で推奨される治療指針について,岩手医科大学・松本主之先生のご教示をお願いします。
【質問者】
三上 栄:神戸市立医療センター西市民病院 消化器内科医長
【A】

さらに,小腸MALTリンパ腫のプロトタイプであるimmuno-proliferative small intestinal disease(IPSID)もHp除菌療法での改善が報告され,本症と腸管感染の関係が強く示唆されました。その後,IPSIDの一部がCampylobacter jejuni感染に起因することも明らかになっています。これに対し,直腸の限局性リンパ増殖疾患とHpやその他の細菌感染の関係には不明の点が多く,しばしばご質問のような疑問が呈されるのが現状です。
従来,直腸リンパ濾胞過形成(いわゆるrectal ton-sil)が自然退縮することは知られていました。一方,直腸MALTリンパ腫に対するHp除菌療法の効果は,わが国を中心としていくつかの報告がみられます。それらの結果を要約すると,確かに除菌療法が奏効する直腸MALTリンパ腫は存在しますが,その効果はHp感染の有無とは無関係のようです。すなわち,現時点では直腸MALTリンパ腫の一部で発育・進展に腸内細菌が関与する可能性があると考えざるをえません。したがって,臨床病期Ⅰにとどまる低悪性度直腸MALTリンパ腫に対しては除菌療法が第一選択と思われます。ただし,治療前に十分な精密検査を施行し,高悪性度成分や他の消化管におけるリンパ増殖性病変がないことを確認することが重要です。
一方,単回の除菌療法が無効な場合,高悪性度成分が明らかでなければ経過観察とし,増大傾向を示す,あるいは高悪性度成分が確認される場合は放射線療法を選択しています。なお,除菌療法後きわめて緩徐に縮小する病変があるので,一定期間,慎重な経過観察を行うよう心がけています。
私自身は,まず除菌療法直後に効果判定を行い,3カ月間隔の内視鏡検査と生検で半年~1年程度経過観察し,追加治療の適応を判断しています。自験例はこのようなアプローチで問題なく経過していますが,さらに症例を集積し,妥当性を検証することが重要と思われます。