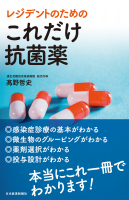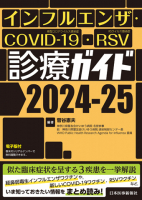お知らせ
近年の日本における結核の疫学および診断 【高齢者結核の主な原因は若年時の潜在的感染。若年者では半数が外国人結核である】

他の先進国と比較し,わが国は結核罹患率が高く,結核疑い症例に出くわす機会も多いと思います。昨今では塾,留置所,日本語学校などでの結核集団発生事例も世間を賑わせています。そこで,現在のわが国の結核疫学情報および結核を疑った際の喀痰検査や補助診断を中心に,国立国際医療研究センター・武藤義和先生のご解説をお願いします。
【質問者】

的野多加志 国立感染症研究所細菌第一部
【回答】
1950年代まで,結核はその罹患率(人口10万人当たりの年間結核発病者数)は500人/10万人/年を超え,「国民病」「亡国病」と呼ばれていました。その後,各種抗結核薬の導入,結核予防会等による啓蒙活動と,保健所を介した直接監視下短期化学療法(directly observed treatment, short-course:DOTS)活動などによりその数は激減し,現在では15人/10万人/年程度にまで低下しています。
最近のわが国の結核の際立った特徴は,「高齢者結核」と「輸入結核」と言えます。高齢者は,高蔓延状態にあった若年時に潜在的に感染し,免疫力が低下してから発病することが多く,超高齢社会のわが国では80歳以上の結核罹患率はいまだ70人/10万人/年を超えており,依然としてハイリスクと言えます。輸入結核に関しては,外国人労働者や留学生などの長期滞在者の発病が増加しており,2015年には,20歳代の若年者の結核のうち半数が外国出生者であると報告されています。特に輸入結核の場合は多剤耐性結核の頻度が高く,通常の結核とマネジメントが違うため必ず専門家への相談が必要です。

残り805文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する