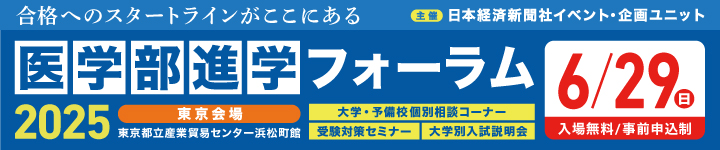お知らせ
心臓サルコイドーシス診療の重要性と難しさ:診断基準の改訂を受けて 【診断基準外であった症例が診断可能に。反面,他の心疾患も診断基準を満たす可能性も】

サルコイドーシスとは,原因不明の全身性肉芽腫性疾患である。肺や眼,皮膚に好発し,自然軽快があるため経過観察となることも多い。しかし,心病変は別である。
心臓での炎症や線維化の進展により,心筋の器質的・機能的障害や,完全房室ブロックなどの伝導障害,心室頻拍などの致死性不整脈が発生し,突然死や難治性重症心不全を引き起こす。そのため心病変では,炎症抑制目的としてステロイド治療が適応となる。しかし,器質的障害が進行した末期にはステロイドの効果は乏しく,早期に診断し適切なタイミングでの介入が求められる。また,完全房室ブロックや心不全の原因がサルコイドーシスであれば原因治療が可能であり,未治療では持続炎症による器質的・機能的障害が進行する。必ず鑑別すべき重要な疾患である。

サルコイドーシスの診断には,長らく「サルコイドーシスの診断基準と診断の手引き─2006」が用いられてきた。2015年に改訂され,16年には日本循環器学会から「心臓サルコイドーシスの診療ガイドライン」が出された。診断には,核医学検査や心臓MRI,特殊なバイオマーカーが必要で,疑わなければ診断には至らない。改訂により,今まで疑わしいのに診断基準を満たさなかった症例や,より軽症な症例を診断できるようになった。一方で敷居が低くなった分,サルコイドーシス以外の心疾患が診断基準を満たす危険性も出てきている。山積する問題の解決には,より多くの症例を診断に導き,経験を蓄積していくことが必要である。
【解説】
小板橋俊美 北里大学循環器内科講師