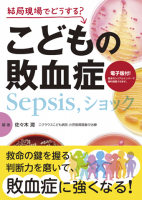お知らせ
日本小児科学会が医療提供体制でシンポ─医療・福祉・保健を包含する新制度を提案
日本小児科学会は4月20〜22日に福岡市で学術集会を開催した。20日に開いた「データに基づく将来を見据えた小児医療提供体制」と題するシンポジウムでは、学会情報管理委員会の杉浦至郎氏(あいち小児保健医療総合センター)が、診療報酬改定が病院小児科や病院全体の収益に及ぼす「影響調査」の結果を発表。小児科領域の深刻な経営状態が浮かび上がった。
調査によると、診療収入は赤字経営の状態にある公的小児病院で上昇しているものの、それ以外の施設では減少。公的小児病院を除く施設では、医師・看護師の人件費割合が診療収入以上に増加していた。人件費割合は病院全体で33.6%であるのに対し、小児科では38.7%に上った。特に、一般病院では病院全体34.9%、小児科45.9%と大きく差が開いており、常勤小児科医師数が少ない病院ほどその傾向が顕著だという。

また、森臨太郎氏(国立成育医療研究センター)は、少子化や予防接種の開発・普及、医療の進歩によって急性期医療の負担が減り、慢性疾患を持つ子ども・家族の生活の質を支える地域医療が重要視され始めていることを強調。生活習慣病やメンタルヘルス対策として健常な子どもたちの成長発育を積極的に支援していく役割が大きく求められていると指摘した。一方で、現在の医療制度では診療報酬の対象が医療に限られるなど、小児医療の変遷に対応できていないと問題視し、「小児の医療・福祉・保健を包含する新制度が必要」との考え方を示した。具体的には、「後期高齢者医療制度のように都道府県ごとに広域連合を形成して保険者となり、妊婦健診・分娩・産後健診・乳幼児健診・予防接種を含む『妊産婦小児保健医療制度(仮称)』を作る」と提案した。