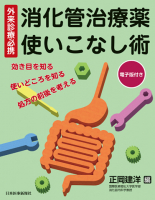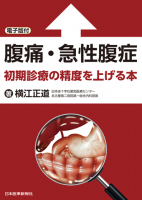お知らせ
経皮内視鏡的胃瘻造設術後の 早期死亡リスク簡易評価法 [学術論文]

経皮内視鏡的胃瘻造設術(PEG)では早期死亡例が少なからず存在する。危険因子を調べるために当院では146例を対象に,目的変数を早期死亡(術後30日以内の死亡)か否か,説明変数を逐次投入法で低栄養(術前3週以内の最新の血清Alb値≦2.7g/dL)および心機能低下(術前30日以内の最新の血中BNP値≧200pg/mL)の有無としてロジスティック回帰分析を行った(後ろ向き研究)。調整オッズ比(95%信頼区間)はそれぞれ8.13(2.8〜23.6),P<0.001と5.06(1.55〜16.5),P<0.01であり,血清Alb値と血中BNP値を指標としたリスク評価法を提唱する。
1. PEG後の早期死亡リスクの客観的な指標を見出す
瘻管造設法は経腸栄養を行う期間が1カ月以上に及ぶ場合に適応となる。経皮内視鏡的胃瘻造設術(percutaneous endoscopic gastrostomy:PEG)は瘻管造設法の第一選択とされるが,造設後1カ月以内の早期死亡例が少なからず存在する。わが国では心・腎機能の低下した症例や重篤な栄養失調・消耗が存在する症例においてPEGの適応を慎重に判断する必要がある1)とされるが,早期死亡リスクを簡便かつ客観的に評価できる指標で示した報告は限られている。そこで,筆者らは当院における症例を対象に研究を行った。

2. 方法─後ろ向き研究,146例から
本研究は後ろ向き研究で,対象は2011年8月1日~2014年3月31日に,当院でシースダイレーターを用いたIntroducer変法によるPEGを行った症例のうち,十分なデータが収集され解析可能であった146例である。いずれの症例も感染症がコントロールされ,出血・凝固系に問題がないことを確認した上でPEGを施行し,易感染性が臨床上大きな問題になるプレドニゾロン10mg/日を超えるステロイド使用例2)や随時血糖250mg/dL以上の糖尿病症例3)は対象に含まれていなかった。
評価項目は,術後30日時点での転帰,年齢,性別,PEGの適応となった原因疾患,術前3週以内の最新の血清アルブミン(Alb)値,術前30日以内の最新の血中脳性ナトリウム利尿ペプチド(brain natriuretic peptide:BNP)値,血清アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)値,血清クレアチニン(Cr)値とし,早期死亡を術後30日以内の死亡,低栄養を血清Alb値≦2.7g/dL,心機能低下を術前30日以内の最新の血中BNP値≧200pg/mL,中等度以上の肝障害を術前30日以内の最新の血清ALT値≧100 IU/L,中等度以上の腎障害を血清Cr値≧2.0mg/dLと定義した。血清Alb値に直接影響を及ぼす肝硬変やネフローゼ症候群の症例は対象に含まれておらず,そのカットオフ値は術後30日時点での転帰との間で作成したROC曲線(曲線下面積0.708)におけるYouden Index(特異度0.863,感度0.524)を採用した。また,Albの血中半減期を考慮して術前3週以内の最新の値を有効とした。一方,血中BNP値のカットオフ値は日本心不全学会が提唱する,治療対象となる心不全の可能性が高いとされる数値を採用した。なお,BNPの血中半減期は約20分と非常に短いにもかかわらず術前30日以内の最新の値を有効としたのは,わが国の保険診療制度では月1回しかBNPを算定できないためである。

残り2,541文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する