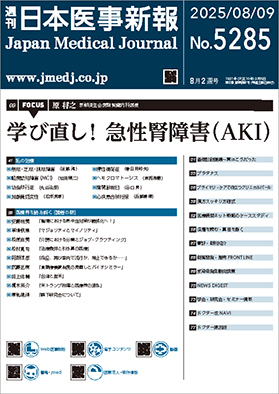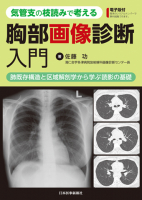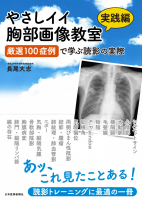お知らせ
肺聴診が現在の診療で持つ意味は?

肺聴診が現在の診療でどのような意味を持つかを,結核予防会・工藤翔二先生にお聞きしたいと思います。
【質問者】

長坂行雄 洛和会音羽病院 洛和会京都呼吸器センター所長
【回答】
【聴診器を通じて医師と患者の信頼関係をつくる重要な役割を果たしている】
ヒポクラテスの時代から続く「身体の中の出来事を知りたい」という医師の願望は,1761年のアウエンブルガー(Auenbrugger,オーストリア)による打診法の発明で幕を開ける。肺聴診はラエンネック(Laennec,フランス)による1816年の聴診器の発明と,その3年後の「間接聴診法」に始まる。次のエポックは,1895年のレントゲン(Röntgen,ドイツ)によるX線の発見であった。さらに,1972年のハウンスフィールド(Hounsfield,英国)とコーマック(Cormack,米国)によるコンピューター断層撮影(computed tomography:CT)の発明とその後の高分解能CT,さらに1966年の池田(日本)による気管支ファイバースコープの開発とそれを用いた気管支肺胞洗浄(bronchoalveolar lavage:BAL),経気管支肺生検(transbronchial lung biopsy:TBLB)など,様々な技術的進歩に支えられて,現在の呼吸器診断は行われている。

残り925文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する