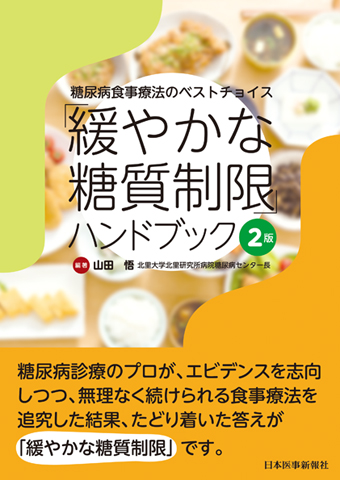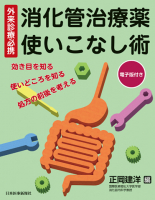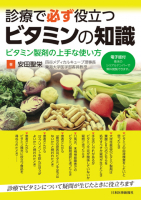お知らせ
食事内容とGERD症状の関連─糖質摂取を中心に

生活習慣の中には食道内酸逆流を引き起こすものがあり,薬物治療に並行して生活習慣を改善していけば有効である
わが国の高齢者胃食道逆流症(GERD)患者の脂質摂取量は少なく,むしろ饅頭,アンパンなどの糖質摂食後に症状が出現することのほうが多い

甘味食品は高浸透圧食品であり,直接食道粘膜刺激を誘発し,食道知覚に作用してGERD症状を誘発するという考え方が一般的である
1. わが国におけるGERDの現況
近年のHelicobacter pylori感染率の低下,食生活の欧米化などに伴い,わが国における消化管疾患の疾患構造に変化が生じていることが報告されている1)。特に,胃食道逆流症(gastroesophageal reflux disease:GERD)は,近年患者数の増加が著しい疾患のひとつであり注目されている。GERDの典型症状は「胸やけ」であり,これが1週間に1回以上生じている患者は,有意に生活の質が障害されていることが既に明らかになっている。したがって,「胸やけ」を生じないようにコントロールすることは,GERD診療における重要な治療目標のひとつとなっている2)。
GERDの治療は,生活習慣の改善・変更,薬物療法,内視鏡的あるいは外科治療の大きく3つに分類される。GERDにおける初期治療および維持療法に,プロトンポンプ阻害薬(proton pump inhibitor:PPI)を第一選択薬とすることは,諸外国やわが国においても既に認められており,日本消化器病学会の「胃食道逆流症(GERD)診療ガイドライン2015 改訂第2版」でも推奨の強さ1(実施することを推奨する)とされている2)。しかし,非びらん性胃食道逆流症(non-erosive reflux disease:NERD)の40~50%,逆流性食道炎の6~15%にPPI治療に抵抗する症例が存在している3)。近年,その対応策のひとつとして生活指導が注目されている4)5)。食道内酸逆流を引き起こす生活習慣の変更・中止を,PPI療法下で行えば有効であるため,生活指導を行うよう提案がなされている2)。GERDの食事指導については,これまで脂質制限を中心に欧米から多くの報告があるが,わが国の高齢者GERD患者では脂質摂取量は少なく,むしろ饅頭,アンパンなどの糖質摂食後に症状を訴えることのほうが多い。本稿では,GERDの病態について概説した後,糖質摂取とGERD症状の関連を中心にその食事指導について解説する。

残り3,507文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する