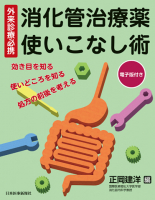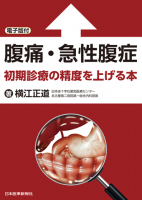お知らせ
Dr. 野中の内視鏡べからず集─とある内視鏡医がH. pylori菌と胃内視鏡検診について考える

●2002年島根医科大学卒業。NTT東日本関東病院消化器内科を経て,現職へ。

1. なぜ除菌するのか?
『日本医事新報社』非常に堅い社名である。そこから毎週刊行されているのが『週刊日本医事新報』らしい。自分自身,本屋でこの名前の雑誌を手に取るか……微妙である。
今回,訳あって手に取ってみたが,意外と読みやすいし,ためになる(意外は失礼かもしれない)。毎週刊行されていることが納得できた。
なぜ,そのようなお堅いお名前の出版社からの依頼原稿を書くことになったのか?話せば長くなるのでやめたい。
簡単に言うと,内視鏡医をめざしている若手医師以外の若手医師やクリニックの先生方にも内視鏡に興味を持って頂けるような堅苦しくない特集を書いてほしいらしい。要は,雑誌の売り上げを上げたいということだろう。当然,なぜ私にそういう期待を持たれたかご存知のない先生方が大半だと思われる。今すぐGoogleで『内視鏡 モテる』と検索頂きたい。
さて,そろそろ本題に入りたい。
皆様,なぜここ数年多くのクリニックでH. pylori除菌が行われるようになったのだろうか?
菓医師,鳥取大学から将来を期待されたエースとして当院に国内留学してきた9年目の医師である。名前が難しく,パソコンの変換で出てこない。それ以外は優秀で素晴らしい若手医師である。
野中:菓先生,なぜここ数年多くのクリニックで除菌療法が行われるようになったと思う?医学的かつ現実的にどういう理由かを,読者の皆様に説明してもらえるかな。
菓:皆様,こんにちは。野中康一先生より,ご紹介頂きました菓裕貴と申します。消化器内視鏡のスペシャリストで,消化器内視鏡に携わる若手医師の中では知らない人はいない野中康一先生のもとで,消化器内視鏡の診断学・治療学について日々勉強しております(野中:この数行,なんか僕が書かせたみたいでイヤらしいのでカットして下さい)。
野中康一先生,この度はこのような機会を頂きまして誠にありがとうございます。
さっそくですが,なぜここ数年で多くのクリニックで除菌療法が行われるようになったか,お話しさせて頂きます。
まずH. pyloriの研究の歴史とはどのようなものか,簡単にお話しさせて頂きます。
1983年にオーストラリアのWarren医師とMarshall医師が胃内にらせん型の菌がいることを発見し,その培養法を確立してLancetに報告しました1)。これが胃内にH. pyloriがいることを証明した最初の論文です。ちなみに1989年にH. pyloriに改名されるまでは,この胃内のらせん型の菌はCampylobacter pyloriと呼ばれていました(PubmedでCampylobacter pyloriに関連した700以上の論文が検索できます)。つまりH. pyloriという名前の細菌が誕生したのは今から30年前ということになります。
その後の多くの研究でH. pyloriは胃炎,消化性潰瘍,胃癌などの様々な疾患に関連することがわかりました。1994年には国際がん研究機関(International Agency for Research on Cancer:IARC)が発行しているIARC発がん性リスク分類で,最も発がん性と関連があるグループ1に分類されます2)。このことからも世界中でH. pyloriの除菌療法が注目されてきました。
わが国で最初に除菌療法が保険適用になったのは約20年前の2000年です。このときは胃・十二指腸潰瘍が対象でした。1990年代の多くの研究で消化性潰瘍の再発率がH. pylori除菌により低下することが明らかになっていたからです3)4)。その後2008年にFukaseらが早期胃癌内視鏡治療後胃の異時性胃癌に対するH. pylori除菌の再発予防効果について報告しました5)。非除菌群に対して除菌群の異時性胃癌発生のハザード比は0.339であり,除菌療法により異時性胃癌の発生が1/3に低下したと報告しています。このデータなどをもとに2010年に早期胃癌内視鏡治療後胃に対して除菌療法が保険適用となりました。このときに免疫性血小板減少性紫斑病(immune thrombocytopenic purpura:ITP),胃粘膜関連リンパ組織(mucosa associated lymphoid tissue:MALT)リンパ腫の2疾患についても同時に保険適用となっています。そして胃癌とH. pyloriの関連性を示す多くの論文とIARC発がん性リスク分類などをもとに2013年2月に世界で初めてH. pylori感染胃炎に対して除菌療法が保険適用となりました。H. pyloriに感染すると,ほぼ全員がH. pylori感染胃炎となるので,実質的にすべてのH. pylori感染患者に除菌療法が実施できるようになりました。さらに「H. pylori感染の診断と治療のガイドライン」では胃癌の予防効果などの観点からH. pylori感染胃炎に対しては除菌療法が強く推奨されています。つまり内視鏡検査を受けてH. pylori感染胃炎が疑われれば,ガイドライン上は除菌療法が強く推奨されるということです。これが「ここ数年多くのクリニックで除菌療法が行われるようになった」一番の理由と考えます。
またわが国で初めて除菌療法が保険適用となってから20年が経ち,除菌療法の有効性が明らかとなってきました。胃癌に対する一次予防効果の検討では胃発癌危険率は除菌群で年率0.21%,非除菌群で年率0.45%とされ,胃癌に対する一次予防効果が報告されています6)。また胃潰瘍に対しては,除菌することで6カ月後の再発率が64.5%から7.9%に減少し,十二指腸潰瘍に対しては6カ月後の再発率が70.6%から4.1%に減少するとされています7)。ほかにもH. pyloriを除菌することによってH. pylori陽性胃MALTリンパ腫の78%で完全寛解が得られ8),胃過形成ポリープの70%が縮小・消失し9),ITP患者の約半数で血小板数が増加すると報告されています10)。これらの疾患は「H. pylori感染の診断と治療のガイドライン」でも除菌療法が強く推奨されています。このような除菌療法の有用性の確立も「ここ数年多くのクリニックで除菌療法が行われるようになった」理由と考えます。また最近の報告では除菌療法で胃腺腫の44%が縮小し,25.9%で完全に消失したとの報告もあります11)。現在も,H. pyloriに対する多くの研究が進行中であり,今後もさらなる新知見の発見,H. pylori除菌療法の有効性が明らかとなることが予想されます。
またABC検診の導入も「ここ数年多くのクリニックで除菌療法が行われるようになった」1つの理由と考えます。ABC検診とは簡便な血液検査である血清H. pylori抗体でH. pylori感染の有無を,血清ペプシノゲン(pepsinogen:PG)法で胃粘膜の萎縮の程度を判断し,胃癌リスクを層別化するものです。H. pylori抗体(-)PG法(-)をA群,H. pylori抗体(+)PG法(-)をB群,H. pylori抗体(+)PG法(+)をC群,H. pylori抗体(-)PG法(+)をD群,除菌後の人をE群に分類します。井上らの報告では,各群で胃癌発見率を検討するとC群で1.87%(39/2089),B群で0.21%(7/3395),A群で胃癌を発見されたのは0人(0/2802)であったと報告しています12)。このように検診の簡便な血液検査でH. pylori感染の有無が調べられるようになり,私の外来にもABC検診の結果をもって,除菌療法を希望して受診される方がたくさんいらっしゃるようになりました。
H. pyloriと胃癌の関連性は医師だけでなく一般の方にも広く周知されてきており,除菌療法を実施する機会が増えてきています。ただ私も時に経験しますが,H. pylori除菌療法によって胃癌にならなくなると勘違いされる方がおられます。H. pylori除菌療法により胃癌の発生がなくなるわけではなく,除菌後にも胃癌リスクは長期にわたり継続しますので13),H. pylori除菌後も内視鏡検査は定期的に受けて頂くようにきちんと説明するように心がける必要があると考えます。
野中:菓先生……文章がかたーーーーい
真面目か??
そう。彼の取り得は真面目ということであった。
本当に真面目で才能がある若手内視鏡医である。
もし私だったら……
「多くのクリニックで除菌をするようになったのは,お金もうけのためです」
とか言ってしまったかもしれない。
皆さん,菓先生がまとめてくれたおかげで,H. pylori除菌療法が普及してきた理由がよくわかりましたね。彼に感謝です(笑)。
さて,ようやくこれから私が今回『日本医事新報』から与えられたテーマ
『内視鏡べからず』という観点からH. pylori除菌により既往感染・未感染者が増えてきた昨今の胃内視鏡検診について考えていきたいと思う。
広辞苑第七版で『べからず』を調べてみると
①……してはいけない。……すべきではない
②……することができない
と記載されている。
内視鏡検査を施行する上で,厳密な意味で『してはいけない』ようなことを世の中の内視鏡医が施行しているとは到底思えない。
広い意味で『しないほうがいいでしょう』あるいは『注意しましょう』という意味あいで,若手内視鏡医あるいは,胃内視鏡検診に携わる多くの医師にとって少しでも役に立つようなポイントを解説したい。