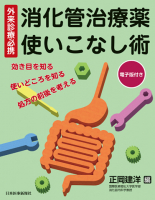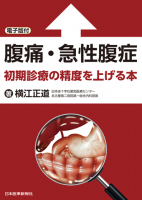お知らせ
胃内視鏡検診の導入

【侵襲性,効率性,経済性から各自治体での導入は順調には進んでいない】
胃癌に対するバリウムを用いたX線検診は,科学的有効性の示された標準的な検診法として,長らくわが国の対策型検診に貢献してきた。しかし近年,検診受診率の伸び悩みとともに,読影医の高齢化と育成不足が顕在化しつつあった。

そうした中,従来の胃X線検査とともに,現在,日常診療で広く普及している胃内視鏡検査が,2015年に公表された国立がん研究センターからのガイドラインで対策型検診として新たに推奨された。これは,胃癌検診を制度として存続させるための必然的な流れであったが,胃内視鏡検診にも種々の問題点が指摘されている。まずは,内視鏡検査は検診としては侵襲性が高い検査で簡便性に問題があり,また,検査が医師によって施行される必要があるため,効率性,経済性に問題がある。こうした問題点のため,各自治体での内視鏡検診の導入は必ずしも順調には進んでいないのが現状である。
加えて,近年わが国では,ヘリコバクター・ピロリ菌感染率の低下に伴い,胃癌罹患率・死亡率の低下傾向がみられ,検診対象者に一律に内視鏡検査を行うことは非効率的で,対象者を絞り込んだ効率的な新しい検診制度の構築が求められている。さらに,今後20年には,胃癌の罹患率,死亡率がさらに大幅に減少し,胃癌は比較的稀ながんとなることが予想され,胃癌検診を,公費が投入される対策型検診として存続させるべきかどうかの議論が必要となる。
【解説】
飯島克則 秋田大学消化器内科/神経内科教授