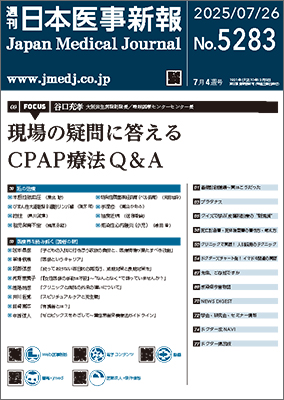お知らせ
直腸粘膜脱症候群[私の治療]
直腸粘膜脱症候群は,排便時のいきみ(straining)が原因となり,顕性あるいは不顕性の直腸粘膜の脱出をきたし,直腸前壁粘膜が肛門管に押しつけられて機械的刺激や虚血によって生じる疾患である。排便時に弛緩すべき恥骨直腸筋や外肛門括約筋が奇異性収縮をきたし,そのために直腸前壁の粘膜が排便時に肛門管に押しつけられることが原因であると言われている。30歳代の比較的若年に多いが,年齢は広く分布しており,男女差はない。
古くは,直腸孤立性潰瘍症候群(Rutterら,1975年),その一亜型は深在性嚢胞性大腸炎(colitis cystica profunda)などとも呼ばれていた疾患で,1983年du Boulayらによりこれらの疾患が同一の病態によるものであると報告され,直腸粘膜脱症候群(mucosal prolapse syndrome:MPS)と呼称されるようになった1)。組織学的には,粘膜固有層の線維筋症(fibromuscular obliteration)が基本的な特徴である。
▶診断のポイント
【症状】
排便時のいきみ,排便困難,残便感,便意頻数(テネスムス),排便時の出血などである。特に排便時のいきみは特徴的な症状であり,排便のためトイレで長時間いきむ傾向がある。
【X線検査】
defecography(排便造影)では,排便時の直腸粘膜重積(internal rectal intussusception)が特徴的であり,上記のいきみ時に生じる恥骨直腸筋の奇異性収縮などが観察される。
【内視鏡検査】
内視鏡所見によって観察される本疾患の示す病変の形態は,潰瘍,隆起,平坦粘膜の粗糙性や発赤など多彩である。隆起性病変は肛門管付近に発生し,潰瘍の形態を示す病変は肛門管から離れた部位に発生する傾向がある2)。平坦型病変の症例では,症状が軽度であることが指摘されている。深在性嚢胞性大腸炎では,粘膜下腫瘍様の形態を示す。
【病理検査】
組織学的には,線維筋症を認めることで確定診断となる。隆起性病変では,組織学的に線維筋症および粘膜上皮の過形成を伴うことが多く,表面は絨毛状の所見を呈し,時に腺癌や腺腫などの腫瘍性病変との鑑別を要することがある。多発することもある。また,深在性嚢胞性大腸炎(MPSの一亜型)では,肉眼的には粘膜下腫瘍様の形態を呈し,粘膜下層に迷入し拡張をきたした腺管上皮が特徴的である。この際も腺癌との鑑別を要する。このタイプの病変においても,線維筋症が認められることによってMPSの診断がなされる。生検は,重要な診断手段であるが,通常の内視鏡生検では十分な組織学的な所見を得ることができないことがあり,特に隆起性病変の場合は,ポリペクトミー,粘膜切除,経肛門的局所切除等の手技を用いて,十分な大きさの生検標本を得ることが重要である。

残り775文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する