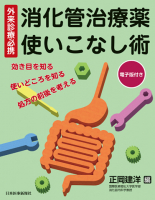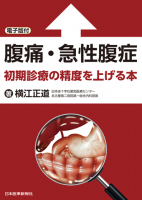お知らせ
腸リンパ管拡張症[私の治療]

蛋白漏出性胃腸症の主要な原因疾患のひとつで,蛋白漏出は高度なことが多い。リンパ流の障害により腸管のリンパ管が拡張・破綻し,消化管内腔に乳びが漏出することで蛋白漏出をきたす。原発性腸リンパ管拡張症と続発性腸リンパ管拡張症に分類される。原発性の要因としてはリンパ管の先天的形態異常(リンパ管形成不全や胸管の閉塞)が,続発性の要因としては腸管リンパ流を障害する様々な器質的疾患がある。末梢血リンパ球減少,低γグロブリン血症による二次性免疫不全状態で予後不良なことがある。
▶診断のポイント
蛋白漏出性胃腸症(低蛋白血症ならびに便中α1-アンチトリプシンクリアランス・蛋白漏出シンチグラフィーによる蛋白漏出の証明)と腸管(白色絨毛など)・腸間膜(浮腫,リンパ節腫大)の形態異常をきたす。

▶私の治療方針・処方の組み立て方
【原発性腸リンパ管拡張症と続発性腸リンパ管拡張症の鑑別】
続発性の要因としては,悪性リンパ腫等の後腹膜腫瘍,後腹膜線維症,腸間膜に発生した結核・サルコイドーシス,クローン病,強皮症,セリアック病,全身性エリテマトーデス,マクログロブリン血症,多発性骨髄腫,慢性うっ血性心不全,収縮性心膜炎,Fontan手術後などがあり,その場合は原因疾患の治療で蛋白漏出性胃腸症が軽快・改善される。なお,続発性腸リンパ管拡張症の中で,腸リンパ管拡張症の症状・所見が基礎疾患の発症に先行する場合があるので,経過観察と定期的な検査フォローアップが重要である。
【形態・障害部位による分類】
近位小腸(特に上部空腸)で病変は最も顕著であるため,上部消化管内視鏡での十二指腸の粘膜所見,生検病理所見により診断できる場合も多い。形態的には多発する白色絨毛,顆粒状隆起,リンパ管腫とケルクリング皺襞の肥厚が認められる。ただ,高脂肪食などの食事による影響で,健常人でも十二指腸粘膜には白色絨毛が認められるので,その場合は低蛋白血症と蛋白漏出の有無の確認が必要である。生検病理検体のヘマトキシリン・エオジン染色,D2-40免疫染色で腸リンパ管の拡張所見があれば確定診断がつく。D2-40は抗ヒトリンパ管内皮抗原モノクローナル抗体である。深部組織のリンパ管が拡張する非白色絨毛型の場合は短縮腫大絨毛のみのため,腹部造影CT検査等の所見も参考に診断する。
Ohmiyaらは白色絨毛を呈さない蛋白漏出性胃腸症の中に,生検組織や剖検組織で腸リンパ管の拡張を呈する疾患があることに着目して,腸リンパ管拡張症(広義の腸リンパ管拡張症)は,以下に二大別されることを提唱した1)。
〈白色絨毛型腸リンパ管拡張症(狭義の腸リンパ管拡張症)〉
粘膜面のリンパ管まで拡張するため,白色絨毛,顆粒状隆起,リンパ管腫とケルクリング皺襞の肥厚が認められる。胃粘膜は正常である。
〈非白色絨毛型腸リンパ管拡張症〉
白色絨毛を呈さず,深部組織のリンパ管が拡張する。非白色絨毛型腸リンパ管拡張症は,内視鏡所見は一見正常であるが,詳細に観察すると,絨毛はやや腫大し丸みを帯びて短縮傾向である。また,胃粘膜が門脈圧亢進症の際にも認められる蛇皮所見(snake-skin appearance)を呈する。
小腸壁肥厚,腸間膜・後腹膜脂肪織濃度上昇,腸間膜・傍大動脈リンパ節腫大において,この2病態で有意差は認められないが,非白色絨毛型のほうが,蛋白漏出の程度が高度である。これは,おそらく罹患範囲が白色絨毛型より広いためと思われる。また,ステロイドの反応性については,白色絨毛型の大部分は無効であるが,非白色絨毛型は反応することが多い。原因は不明であるが,自然寛解することもある。

残り1,270文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する