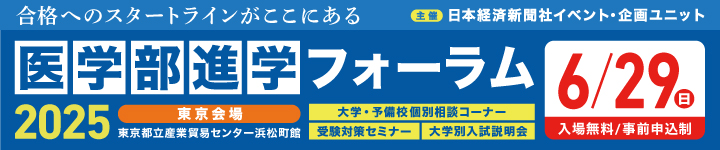お知らせ
急性心不全[私の治療]

心不全とは,何らかの原因で心ポンプの働きが低下する状態である。これが急激に生ずると,2つの異常が様々な程度で生体に現れる。1つは,川でいうと下流に血液が十分流れない「低心拍出」であり,灌流低下に伴い臓器障害が進む。もう1つは,下流にはけない血液が上流にたまる「うっ血」であり,中でも肺うっ血は肺でのガス交換を妨げ呼吸困難をきたす。
▶診断のポイント
【症状】
息切れが重要で,特に発作性夜間呼吸困難が心不全に特異的である。就寝後1~2時間くらいに息苦しさを感じ,坐位で軽減する。

【身体所見】
肺ラ音と下腿浮腫は判断が容易であるが,非特異的である。むしろ心血管内のうっ血所見として,心ギャロップと頸静脈怒張を重視する。頸静脈怒張は,坐位や立位での内頸静脈の怒張を呈し,「起き上がった状態での頸の皮膚の揺れ」として認識できる。
【検査】
BNPが100pg/mL以上では心不全を鑑別診断に入れ,400pg/mL以上では高率に心不全を疑う。心エコー図では左室拡張末期圧の上昇を反映した,下大静脈径,三尖弁逆流圧較差(TRPG),僧帽弁流入ドプラ波形指標(E/e’)の3指標を重視する。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
【初期対応】
患者救命と苦痛改善を最優先する。すなわち,酸素化と血行動態の立て直しを図りつつ,急ぎ病態の把握を進める。初動の遅れは予後の悪化につながり,急性冠症候群のごとく分刻みの迅速性が求められる。簡便な病態把握法として,初期収縮期血圧(SBP)を参考にしたクリニカルシナリオ(CS)が普及してきた。SBP<100mmHg(CS3)は臓器低灌流とみなし,強心薬を用いる。SBP>140mmHg(CS1)は血管収縮とみなし,血管拡張薬を用いる。SBPが100~140mmHg(CS2)では,体液貯留が主体の例が多く,利尿薬で対処する。
【病型に基づく治療の方向づけ】
Nohria-Stevenson分類は,身体所見に基づいた心不全患者のリスクプロファイルとして優れ,治療法の選択にも有用である。うっ血に対しては血管拡張薬と利尿薬を,末梢循環不全ではカテコラミン系薬の静脈内投与を行う。
【予後への配慮】
急性増悪の繰り返しにより,心不全予後は相加的に悪化する。急性期イベントに対し最善の対処をすることで,心不全全体の予後を改善できる。急性期治療は慢性期治療でもある,との考えが浸透してきた。

残り1,495文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する