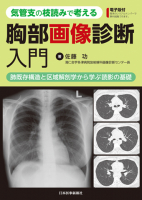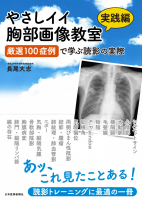お知らせ
院内肺炎[私の治療]

院内肺炎とは,入院後48時間以上経過した患者に発症した肺炎である。人工呼吸器関連肺炎(ventilator-associated pneumonia:VAP)や誤嚥性肺炎を含む。基礎疾患(免疫不全状態,抗癌剤治療中の好中球減少状態,ステロイドや免疫抑制薬投与による細胞性免疫不全状態,不顕性誤嚥も含む誤嚥)を持つ症例が多く,予後が悪い。メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(methicillin-resistant Staphylococcus aureus:MRSA)や緑膿菌,腸内細菌属の耐性化リスクを有する菌が原因菌となりうる。
▶診断のポイント
感染症以外の要因による肺炎(薬剤性や間質性)や心不全などを鑑別する。胸部異常陰影の出現に加えて,発熱,白血球数異常,膿性分泌物のうち2項目を満たす症例を院内肺炎と診断する。治療前に重症度分類を行う。耐性菌が原因菌になることが多く,その同定,リスクを把握する。

▶私の治療方針・処方の組み立て方
まず広域スペクトラムの抗菌薬を使用し,その後狭域スペクトラムの抗菌薬を使用するde-escalation治療が行えるかどうかが重要である。抗菌薬適正使用を遵守するべきではあるが,重症症例では最初の段階ではカルバペネム系抗菌薬を使わざるをえない。アミノグリコシド系抗菌薬は腎機能障害を生じることも多く,可能であれば使用しない。がん末期や老衰などの終末期患者に対しては,回復する見込みが少なく,個人の意思を十分に確認してから治療を行う。
まず重症度分類を行う。①生命予後因子を検討し,その後②肺炎重症度規定因子を組み合わせて,③重症度を決定する。重症症例の場合,④MRSA保有リスクを検討する。
原因微生物が同定され,感受性が判明した時点で de-escalationが可能かどうか検討する。適正な抗菌薬が投与されれば,緑膿菌やMRSAなどを除き,治療期間は7~10日である。
【生命予後予測因子】
1)I(Immunodeficiency):悪性腫瘍または免疫不全状態
2)R(Respiration):SpO2>90%を維持するためにFiO2>35%を要する
3)O(Orientation):意識レベルの低下
4)A(Age):男性70歳以上,女性75歳以上
5)D(Dehydration):乏尿または脱水
【肺炎重症度規定因子】
1)CRP≧20mg/dL
2)胸部X線写真陰影の広がりが一側肺の2/3以上
【重症度】
・生命予後予測因子が2項目以下で肺炎重症度規定因子なし:軽症群
・生命予後予測因子が2項目以下で肺炎重症度規定因子あり:中等症群
・生命予後予測因子が3項目以上:重症群
【MRSA保有リスク】
1)長期(2週間以上)の抗菌薬投与
2)長期入院の既往
3)MRSA感染やコロニゼーションの既往

残り753文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する