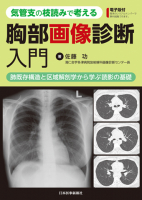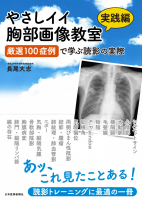お知らせ
放射線肺炎[私の治療]

放射線肺炎は,主に肺癌や乳癌など胸部の放射線治療後に生じる肺障害である。電離放射線が肺に照射されると,直後よりフリーラジカルが形成され,毛細血管透過性亢進による肺胞間質の浮腫,種々のサイトカインの放出が起こる。さらに,リンパ球・形質細胞などの炎症性細胞の浸潤による肺胞隔壁の肥厚がみられ,間質性肺炎を生じる。その後,線維芽細胞が活性化され線維化へと進む。放射線照射野内に生じることが多いが,照射野外に進展する症例もある。
▶診断のポイント
軽度の場合は無症状であることも多いが,労作時呼吸困難,乾性咳嗽,発熱が三徴である。多くは照射終了後1~3カ月程度で発症するが,照射直後や5~6カ月程度経過してから発症する場合もある。

理学的所見としては聴診での捻髪音,胸膜摩擦音が照射野付近で聴取される。生化学的検査ではKL-6,SP-Dの増加が有用である。鑑別診断のために気管支肺胞洗浄(BAL)が行われることもあるが,リンパ球増多が多くみられる以外に本症に特異的な所見はない。
画像診断では特にCT所見が特徴的であり,発症初期には照射野内の肺にすりガラス影,網状影などの間質陰影が出現する。照射野と一致して肺区域や肺葉などの解剖学的境界と無関係に広がることが特徴となるが,最近の強度変調放射線治療では,三次元的な線量分布図を参照する必要がある。さらに時間が経過すると線維化期となり,線状の瘢痕化や濃度上昇,肺容積の減少を認めるようになる。容積減少が著明な場合,呼吸機能が低下する。特に診断に迷う発現初期には,初期のすりガラス影が照射範囲内から出現しているか否かが診断の鍵となり,鑑別疾患としては感染症,がん性リンパ管症・腫瘍浸潤,薬剤性肺炎,その他の間質性肺炎,心不全などがある。

残り1,179文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する