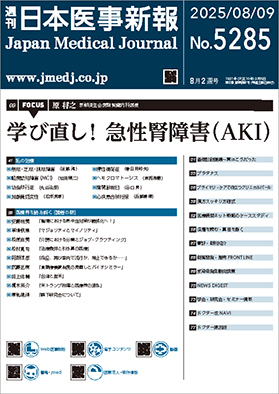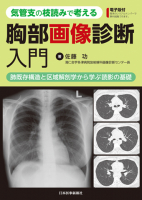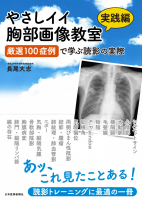お知らせ
好酸球性肺炎[私の治療]

好酸球性肺炎は,肺の間質および実質に好酸球が浸潤する疾患の総称である。発症の原因が薬剤,真菌,寄生虫など明らかな場合もあるが,原因がはっきりしない特発性のものもあり,本稿では後者を扱う。特発性は急性と慢性にわけられるが,両者の臨床像は大きく異なっており,別の疾患として扱われる。
急性好酸球性肺炎は1週間以内の急性の経過で発症し,わが国では喫煙との関連が示唆される報告が多い。慢性好酸球性肺炎は,典型例では月単位の経過で咳嗽,発熱などの症状が出現し,多くの例でアトピー素因がある。
▶診断のポイント
【急性】
1週間以内の急性経過で発熱や呼吸困難を認め,呼吸不全を呈する。発症1カ月以内に喫煙を開始または再開していることが多く,また喫煙本数の増加がきっかけとなることもあるため,喫煙歴の詳細な聴取が重要となる。最近では加熱式たばこや電子たばこが誘因の報告もみられる。多くの症例でアトピー素因はみられない。

梢血好酸球は特に発症早期には正常であり,発症1週間程度遅れて増加してくる。受診時点では末梢血好酸球数が正常であることが多く,注意が必要である。画像的には両肺野のびまん性のすりガラス影,浸潤影を認め,さらに小葉間隔壁の肥厚を伴う。しばしば胸水貯留も認める1)。気管支肺胞洗浄液中の好酸球は25%以上に上昇しており,診断に有用である。
感染症,肺水腫,急性呼吸窮迫症候群(ARDS)などとの鑑別が問題となることがある。
【慢性】
湿性咳嗽,発熱,呼吸困難,体重減少,盗汗などの症状が,月単位の経過で出現する。急性好酸球性肺炎と異なり,アトピー素因を背景に持つ症例が多い。
末梢血では好酸球数上昇がみられ,炎症反応上昇もみられる。背景にアトピー素因を持つ症例が多く,IgE値の上昇もみられる。胸部単純X線写真では末梢優位の浸潤影を認め,「逆肺水腫像」とも呼ばれる。胸部CTでは胸膜直下優位で斑状に非区域性の斑状影・浸潤影を認める。急性好酸球性肺炎と異なり,胸膜病変や胸水を伴う症例は少ない1)。気管支肺胞洗浄液(BALF)中の好酸球増多が診断に有用であり,カットオフ値は診断基準によって異なるが,多くの症例で25%以上である。
鑑別疾患として,薬剤性肺炎,真菌感染,寄生虫感染,その他の間質性肺疾患などの可能性は念頭に置く必要がある。また,肺外病変を認める場合は,好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)や好酸球増多症候群(HES)の可能性を考える。

残り1,572文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する