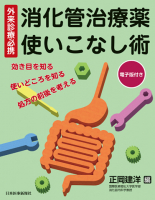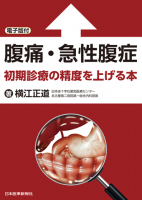お知らせ
放射線性腸炎[私の治療]

放射線治療により照射部位に腸管が含まれた際に生じる腸炎のことである。前立腺癌や子宮頸癌などの骨盤内悪性腫瘍に対して放射線治療を行う場合は,腸管が照射部位に含まれることから,直腸やS状結腸に放射線性腸炎を生じることが多い。照射中から2~3カ月以内に認められる早期障害と,照射後数カ月以降に認められる晩期障害がある。
▶診断のポイント
【症状】
血便や下痢・腹痛などの非特異的な症状を自覚する。他疾患との鑑別が必要であるが,放射線治療歴があればその時期や照射部位を確認することが重要である。

【検査所見】
早期障害は放射線治療時期との関連を問診等から確認すれば,臨床的に診断される。晩期障害では,放射線治療歴がある場合には積極的に疑う。下部消化管内視鏡を施行し,放射線照射部位と毛細血管拡張などの内視鏡病変範囲が一致することを確認する。稀に,小腸に病変を呈する場合もあるが,その際にはバルーン内視鏡等で小腸内を観察する。頻度は高くないが,潰瘍・狭窄・瘻孔を伴う場合もある。放射線性腸炎の発症から経過が長い場合には,鉄欠乏性貧血を認める。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
早期障害は放射線照射による粘膜浮腫が原因であり,一過性であることから対症療法を中心に行う。
晩期障害は非可逆的な病変であり完治は困難と考え,出血のコントロールが治療目標となる1)。出血が少量の場合は,硬便などによる物理的接触による出血を避ける。また,鉄を補充し,鉄欠乏性貧血に対処する。これら対症療法でも出血量が多く貧血が進行する場合には,内視鏡的止血術を考慮する。アルゴンプラズマ凝固法(argon plasma coagulation:APC)が有効であるが,効果は一時的であり反復治療を要する場合も多い2)。内視鏡治療でもコントロール不良の際には,最終的には外科的切除となる。しかし,外科的切除は侵襲が大きいため,他の内科的治療を医療環境に応じて適宜施行する。主には注腸による薬剤投与である。また,高圧酸素療法の有効例も報告されており3),患者と相談しながら内科的治療を順次施行していくこととなる。

残り1,067文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する