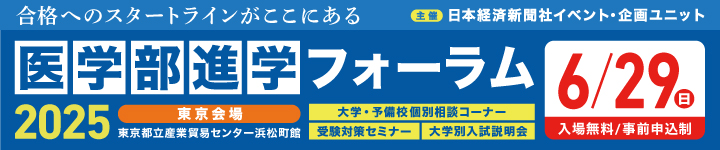お知らせ
【文献 pick up】SGLT2阻害薬は心不全患者のどのような自己評価健康状態を改善するのか―RCT“DELIVER”後付解析/JAMA Cardiol誌

SGLT2阻害薬は「左室駆出率≧40%」心不全[HFmr/pEF](40%未満からの回復例[HFrecEF]も含む)の 「心不全増悪(入院・救急受診)・心臓血管系死亡」を有意に抑制するだけでなく「患者評価健康状態」も有意に改善することが、ランダム化比較試験(RCT)"DELIVER"で確認されている。
DELIVER試験で「健康状態」の患者評価に用いられたのは、カンザスシティ心筋障害質問票(KCCQ)である。患者本人が23項目の質問に回答し、7領域の改善度が評価される(なおこれら7領域は「症状」「身体・社会生活制限」「QOL」の3領域に大別される[Spertus JA, et al. 2020])。

ではSGLT2阻害薬は具体的にKCCQのどの項目を改善したのか―。その点を詳細に解析した報告が後付解析ながら5月20日、JAMA Cardiol誌に報告された。報告者は米国・ブリガム・アンド・ウィミンズ病院のAlexander Peikert氏らである。
解析対象はDELIVER試験に参加したHFrec/mr/pEF 6263例中、試験開始時KCCQデータが得られた5795例である。
平均年齢は71.5歳、42.3%が女性だった。
またループ利尿薬は72.3%で使用されており、EFが低いほど服用率は高い傾向があった[Chatur S, et al. 2023]。
そして今回の本題であるKCCQの変化だが、試験開始8カ月後、SGLT2阻害薬群ではほぼすべての項目で、プラセボ群に比べ有意な改善を認めた。
その中で最も改善幅が大きかったのは「下肢浮腫」である。次いで「息切れによる睡眠障害」「息切れによる活動制限」だった。いずれも「うっ血」との関連が強い。
一方「疲労による活動制限」や「労作・家事」はSGLT2阻害薬群で有意改善を認めるも、改善幅は前3者ほど大きくなかった。また「心不全症状の変化」は両群間で有意差を認めなかった。
なお、評価項目ごとにSGLT2阻害薬による改善幅に差が生じた理由は、考察されていなかった。
DELIVER試験はAstraZenecaから資金提供を受けて実施された。