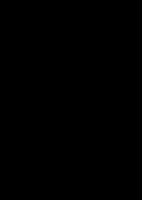お知らせ
■NEWS 【米国糖尿病学会(ADA)】糖尿病発症前の認知機能とβ細胞機能が逆相関?―DPP/DPPOS試験追加解析

よく知られている通り、2型糖尿病(DM)例では認知機能低下リスクが上昇しており、45%が軽度認知障害を合併しているとの観察研究メタ解析[You Y, et al. 2021]もある。
この認知機能低下をもたらす要因は糖代謝異常だけではなく、インスリン動態の異常も関与しているようだ。

6月23日から米国サンディエゴで開催された米国糖尿病学会(ADA)第83回学術集会において米国・コロラド大学のAllison L. B. Shapiro氏が、DPP/DPPOS試験データを用いた解析結果として報告した。
解析対象となったDPP/DPPOS研究は、2型DM発症高リスク例をメトホルミン群、プラセボ群、生活習慣改善強化群の3群にランダム化し、平均2.7年間DM発症抑制作用を比較後(DPP試験)、オープンラベルで観察を続けている研究である(DPPOS)[NCT00038727]。
今回の解析対象はその中の、試験開始12年後も2型DMを発症しておらず、かつ試験開始時のインスリン評価と開始時・終了時の認知機能評価データが揃っていた1054例である。
DPP試験開始時の平均年齢は51.8歳、認知機能評価時は63.7歳であり「認知機能を検討する研究としては比較的若年だ」とShapiro氏は指摘している。
これら1054例を対象に、β細胞機能(インスリンインデックス[IGI])、インスリン感受性(「1/空腹時インスリン値」)が、その後の認知機能変化に与える影響を検討した。
β細胞機能とインスリン感受性が認知機能に与える影響の検討にあたっては、「DPPにおける治療群」「年齢」「性別」「教育を受けていた期間」だけでなく、「BMIの経時的変化」と「HbA1cの経時的変化」も変数として組み込んだ(多変量解析)。
その結果、「記憶」(Verbal Learning Test評価)については「直後再生」「遅延再生」のどちらも、その変化はβ細胞機能とインスリン感受性のいずれとも相関していなかった。
有意相関を認めた因子は「年齢」「教育期間」と「性別」(女性のほうが低リスク)のみである。観察期間中の「BMI」や「HbA1c」の変化とも相関していなかった。
一方、「実行機能」(Digital Symbol Substitution Test評価)は、「β細胞機能」と有意な逆相関を示した、一方、「インスリン感受性」とは有意相関を認めなかった。
またそれ以外の因子では「年齢」「教育期間」「性別」に加え「HbA1cの変化」も、「実行機能」と有意な逆相関を示した。インスリン感受性や糖代謝異常と独立して、β細胞機能が「実行機能」と逆相関していた形である。
「記憶」とβ細胞機能間に相関を認めなかった理由としてShapiro氏は、記憶障害は今後、遅延して発現するのではないかとの見解を示している。
さてβ細胞機能と実行機能が逆相関する機序として同氏は、高インスリン血症による脳のインスリン抵抗性惹起が認知機能低下をもたらす(動物実験に支持データありとのこと)、あるいは高インスリン血症が高トリグリセライド血症を来たし、アテローム動脈硬化性疾患が進展。結果として血管性認知症リスクが上がる可能性を考えているという。
なお既報ではインスリン抵抗性が認知機能低下のリスクとする報告が多い。これについて同氏は、それら報告のほとんどが2型DM発症例を対象としている、β細胞機能評価に空腹時インスリンを用いている(IGIは糖負荷後のインスリン分泌で評価)―などの点が本研究と異なると指摘している。
本解析に関し開示すべき利益相反はないという。