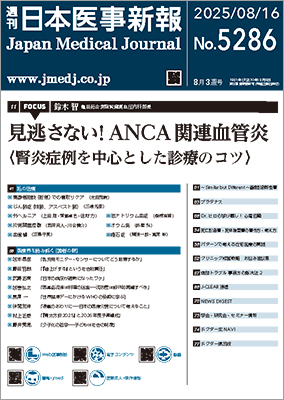お知らせ
潰瘍性大腸炎の診断と治療:最近の動向[J-CLEAR通信(156)]

潰瘍性大腸炎(ulcerative colitis:UC)は10~30代前半に好発する大腸の慢性炎症性疾患であり,現在の患者数が全国に22万人以上と推定されているが,いまだ原因不明で,国の特定疾患に指定されている。最近判明してきた病態として腸管粘膜でマクロファージ,好中球,Tリンパ球などの白血球が炎症を引き起こす中心的役割を担っていることがわかってきたが,これら炎症細胞が血管内皮細胞に接着し,組織内に浸潤し,粘膜側へ遊走して大腸粘膜の炎症が惹起されることが想定されている。
この経路をターゲットとした生物学的製剤や低分子化合物が次々と開発されて,新たな治療指針も提案されている。

本稿では,主に2021年に発表された厚生労働省の「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」(久松班)の報告書である「潰瘍性大腸炎・クローン病診断基準・治療指針」1)と,日本消化器病学会から発表されている「炎症性腸疾患(IBD)診療ガイドライン2020 改訂第2版」2)を参考にして,UCの診断と治療に関する最近の話題について概説する。