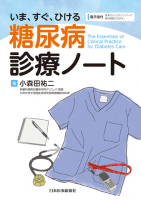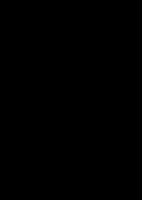お知らせ
■NEWS【ADA報告】GLP-1-RAによる過体重/肥満例CVイベント抑制に減量は無関係?―RCT ”SELECT”追加解析
昨年の米国心臓協会(AHA)学術集会でランダム化比較試験(RCT) “SELECT”が報告され、「過体重・肥満例へのGLP-1-RAを用いた減量治療が心血管系(CV)イベントを抑制した」との結果が注目を集めた [Khera A, et al. NEJM. 2023] 。しかし追加解析の結果、「減量によるCVイベント抑制」には疑問符がついたようだ。6月21日から米国オーランドで開催された米国糖尿病学会(ADA)にて、テキサス大学(米国)のIIdiko Lingvay氏が報告した。
なお同時に報告されたSELECT試験の追加解析では、GLP-1-RAによる血糖改善作用も、CVイベント抑制との相関が認められなかった [Lingvay I, et al. Diabetes Care. 2024] 。そのため本演題が報告されたセッションでは、GLP-1-RAによる過体重/肥満例のCVリスク軽減をもたらしたのは「減量」や「糖代謝改善」というより「多面的作用」によるものという認識が主流となっていた。

SELECT試験 [既報分]
【対象】
すでに報告されている通り、SELECT試験の対象は、「45歳以上」で「CV疾患既往」のある「BMI≧27 kg/m2」だった「非糖尿病(DM)」 1万7604例である。平均年齢は61.6歳、男性が72.3%を占めた。BMI平均値は33.3kg/m2で全体の71.5%が「≧30 kg/m2」だった。
【方法】
これら1万7604例はGLP-1-RAのセマグルチド(2.4 mg/週)群とプラセボ群にランダム化され、二重盲検法で平均39.8カ月間観察された。
【結果】
その結果、1次評価項目である「CV死亡・心筋梗塞・脳卒中」リスクについて、セマグルチド群はプラセボ群に比べ有意に低値となった(ハザード比:0.80、95%信頼区間[CI]:0.72-0.90)。治療必要数(NNT)は「67」である。なおセマグルチド群におけるこれらイベントの減少は試験開始直後から始まり、減量作用が著明となる以前に観察された(本誌AHA報告 [拙稿] )。
・SELECT試験 ADA報告
【方法】
今回報告されたのは探索的追加解析である。試験開始後20週までに「5%以上」減量した例と減量しなかった例に分け、20週以降の「CV死亡・心筋梗塞・脳卒中」リスクを比較した。
【結果】
・セマグルチド群
セマグルチド群では62%が20週までに「5%以上減量」していた。しかしこれら「減量5%以上」例における20週以降の「CV死亡・心筋梗塞・脳卒中」発生率曲線は、「減量5%未満」例とほぼ重なり合ったままだった(発生率に差なし)。Lingvay氏は(セマグルチド群では)「試験開始から20週でどれほど減量するかは(CV転帰改善の観点からは)重要でない」とコメントしている。
・プラセボ群
プラセボ群でも興味深い結果が得られた。当初20週で「減量5%以上」例のほうが「減量5%未満」例に比べ、「CV死亡・心筋梗塞・脳卒中」発生率は高かった(検定示されず)。試験開始後4年間観察できた例で比較すると、「減量5%以上」例のほうが「CV死亡・心筋梗塞・脳卒中」発生率はおよそ2%高かった。この結果についてLingvay氏は、「意図しない減量はおそらく有用(beneficial)ではない」と述べている。
ただし本試験ではセマグルチド群、プラセボ群ともCVリスクを減らすべく積極的な生活改善指導(食事と身体活動性を含む)を受けていた。なおフロアからは、減量効果の有無を判定するのに上記の「減量5%」という基準値は低すぎるのではないか、との声も上がっていた。
【考察】
上記結果とは別に、指定討論者であるインペリアル・カレッジ・ロンドン(英国)のShivani Misra氏は、SELECT試験の対象があくまでCV疾患既往例である点を強調していた。
ちなみに本学会で報告されたSURMOUNT-OSA試験(本サイトADA報告 [拙稿] )では、SELECT試験と使用薬剤は異なるものの、肥満例の体重を実薬群でプラセボ群に比べ年間約15 kg低下させても、1年間のCVイベント(有害事象としてカウント)発生率はプラセボ群と同等だった(両群ともほぼ皆無)。同試験は重症夜間無呼吸例を対象としているが、直近のCV疾患既往例は除外されている。
SELECT試験はNovo Nordiskから資金提供を受けて実施された。同社は試験プロトコル作成にも参加し、試験データベース管理と統計解析を担当した(統計は第三者がレビュー)。また同社からは4名が治験運営委員(Steering Committee)、7名が原著者として参加した。