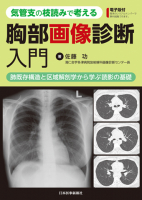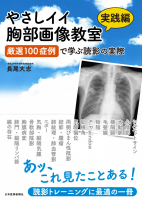お知らせ
特発性肺線維症と周辺疾患の治療法 【IPFにニンテダニブが使用可能となったが,近縁疾患では症例ごとに治療しているのが現状】

特発性肺線維症(IPF)は,原因が明らかでない慢性線維化性間質性肺疾患の中で最も多く,予後不良の疾患である。わが国の近年の報告では,初診時からの生存期間中央値は8年9カ月,症状出現後の生存期間中央値は5年9カ月である(文献1)。これは過去の報告よりは長い生存が得られるようになったことを示唆する。しかし,IPFの予後が不良であることに変わりはなく,悪性腫瘍と比べても5年生存率は不良である。
2014年にピルフェニドンとニンテダニブのIPFにおける大規模臨床試験での有益性の結果が掲載された(文献2,3)。これを受け,わが国ではピルフェニドンに加え,15年8月よりニンテダニブが使用可能となった。ピルフェニドン,ニンテダニブおよびその併用療法,N-アセチルシステイン,そして従来のステロイド,免疫抑制薬の位置づけについてはまだ答えがないが,予後改善に期待が持たれる。
慢性過敏性肺炎,強皮症に伴う間質性肺炎,特発性非特異性間質性肺炎などの近縁疾患,自己免疫疾患の症候を有する間質性肺炎,気腫合併IPF,合併症を有するIPF,高齢で外科的肺生検ができないsuspicious of IPFなど,大規模臨床試験から外れる症例の治療法はさらに難しく,これらのnon-pure IPFでは,個々の症例で専門医が最善の治療選択を考え治療しているのが現状である。
【文献】
1) Bando M, et al:Respir Investig. 2015;53(2):51-9.
2) King TE Jr, et al:N Engl J Med. 2014;370(22):2083-92.
3) Richeldi L, et al:N Engl J Med. 2014;370(22):2071-82.