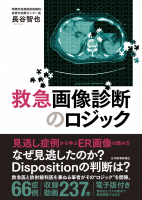お知らせ
(2)熱中症の鑑別診断 [特集:熱中症対策2014]
熱中症の診断には発症状況,患者背景などの情報が不可欠である
熱中症は緊急疾患であり,疑ったときは治療と鑑別診断を同時進行で進めていく
熱中症はほかの鑑別すべき疾患を除外して確定診断とするべきであり,安易に“熱中症”と診断せず緊急性のある疾患として見きわめていかなければならない
1. 早期診断,早期治療の重要性
2014年は6月に入るや否や一部地域で35℃を超す猛暑日となり,異例の早さで熱中症患者が発生している。
熱中症は緊急疾患であり,早期診断,早期治療が重要である。特に重症例は健康な若年者でも死に至り,たとえ生存しても高次機能,小脳症状など,中枢神経への重大な後遺症が生じることがある。その一方で熱中症は,比較的予後は良く,治療に反応しやすい病態でもあるので,いかに早期に診断し治療を開始するかが重要となる。
暑熱環境下での運動,訓練時に若年者が発症した場合,つまり労作性熱中症では,その多くは現場から熱中症と診断されて医療機関に搬送されるので,鑑別診断に悩むことは少ない。ただし,そのような場合でも発症前に倦怠感,ふらつきなどの前兆があるので,発症状況について本人および周囲の者からの病歴聴取を怠ってはならない。
鑑別診断で苦慮するのは,古典的熱中症と言われる日常生活中に発生した症例である(表1)。労作性と同様,発症状況,患者背景などの情報を丁寧に収集することに加えて,臨床症状,検査結果などから,熱中症を疑い,また,熱中症が原因なのか結果なのかを判断しなければならない。安易に熱中症と診断するのではなく,感染症,甲状腺クリーゼ,てんかん(痙攣重積)などの考えうる鑑別疾患,特に緊急性のある疾患を丁寧に除外していく。

2. 熱中症の重症度における新分類
熱中症には熱疲労や熱痙攣など細かな症候群的な分類があり,医療従事者でさえ戸惑うことがある。かつては熱中症の3大条件として①意識障害,②40℃以上の高体温,③発汗停止,が挙げられていたが,この条件で診断していると手遅れになることが危惧される。そこで,日本救急医学会および日本神経救急学会から症状の重症度における新分類が提唱された。軽症から重症までをⅠ〜Ⅲ度とし,特にⅢ度の重症では,意識障害,腎障害,肝障害,播種性血管内凝固症候群(disseminated intravascular coagulation:DIC)のいずれかが認められるものとして非常に簡潔明瞭となった(本特集19ページ,表1を参照)。これは早期治療へつなげる有効な手法と言えるだろう。特に意識障害の有無は現場ですぐに判断でき,医療従事者のみならず,一般市民でも重症度を認知できるため,迅速な救急要請につながる情報となりうる1)。ただし,早期診断が得られる反面,ほかの病態を見逃す可能性も増すということを認識しておかなければならない。

残り3,832文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する