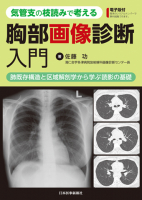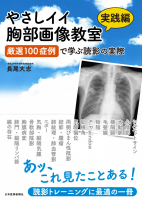お知らせ
医療・介護関連肺炎(NHCAP)は市中肺炎(CAP),院内肺炎(HAP)どちらに準じて治療を行うべきか?【米国と起因菌が大きく異なるわが国では,CAPに準じて治療を選択すべき】

日本呼吸器学会の新しい「成人肺炎診療ガイドライン 2017」では,医療・介護関連肺炎(nursing and healthcare associated pneumonia:NHCAP)は院内肺炎(hospital-acquired pneumonia:HAP)と一緒にされてHAP/NHCAPと市中肺炎(community-acquired pneumonia:CAP)の2つに大別して診療を行うことが記載されています。このようにNHCAPは欧米との位置づけが正反対となりましたが,NHCAPはCAP,HAPどちらに準じて治療を行うべきか,琉球大学・藤田次郎先生のご教示をお願いします。
【質問者】

青島正大 医療法人鉄蕉会亀田総合病院呼吸器内科 主任部長
【回答】
肺炎は,2011年における日本人の死因で第3位の位置を占めました。この要因として,人口の高齢化が最も大きな要因であることは言うまでもありません。2017年に公表された「成人肺炎診療ガイドライン 2017」では,肺炎を大きく2つに分類しています。「CAP」と「HAP+NHC AP」です。ご質問にある通り,このガイドラインでは,NHCAPはHAPと同列に扱われています。
わが国の肺炎診療は,医療アクセスおよび医療資源の点からもきわめて恵まれた状況にあります。欧米各国およびわが国から報告される医療ケア関連肺炎(healthcare-associated pneumonia:HCAP,わが国のNHCAPと若干定義が異なることに留意)の論文において起炎菌の頻度を見ると,興味深いことに気づきます。たとえば,米国の施設においては,HCAPの起炎菌の約半数が黄色ブドウ球菌であり,しかもその半分以上がメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(methicillin-resistant Staphylococcus aureus:MRSA)だと報告されています1)。この数字はわが国では異常であり,医療訴訟にならないか心配になるほどです。

残り917文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する