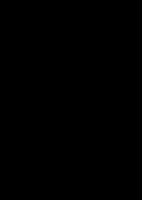お知らせ
汎下垂体機能低下症[私の治療]

下垂体前葉からは副腎皮質刺激ホルモン(ACTH),甲状腺刺激ホルモン(TSH),成長ホルモン(GH),卵胞刺激ホルモン(FSH),黄体刺激ホルモン(LH),プロラクチン(PRL)が分泌される。腫瘍性疾患(下垂体腺腫,頭蓋咽頭腫,胚細胞腫など),出産時大量出血の循環障害(シーハン症候群),炎症性疾患(リンパ球性下垂体炎など)や薬剤(ステロイド,免疫チェックポイント阻害薬)などのため,PRLを除くすべての分泌が障害され,その標的臓器(副腎皮質,甲状腺,肝臓,性腺)のホルモン分泌が低下したものを「汎下垂体機能低下症」と言う。すべてではないが複数のホルモン分泌障害を示すものを「複合型下垂体機能低下症」,1種類のみのホルモン分泌障害を「単独欠損症」と称する。腫瘍性,特に視床下部障害の場合に,血中PRLは上昇する。障害の範囲が大きく,視床下部~下垂体後葉に及ぶ場合には中枢性尿崩症を合併する。
▶診断のポイント
下垂体前葉ホルモンとその標的臓器のホルモン〔ACTHとコルチゾール,TSHと遊離T4,GHとインスリン様成長因子1(IGF-1),FSH・LHとエストラジオールあるいはテストステロン〕が低値となり,各ホルモンに対する分泌刺激試験において低反応を呈する。ACTH刺激にCRH試験やインスリン低血糖刺激試験(ITT),TSHにはTRH試験,GHにはGHRP-2試験やITT,FSHとLHにはLHRH試験を用いる。1日蓄尿による尿中遊離コルチゾール低値も重要所見となる。中枢性尿崩症の合併に留意する。コルチゾール低下症と中枢性尿崩症を合併する場合は,多尿を認めない例もある(仮面尿崩症)。

▶私の治療方針・処方の組み立て方
下垂体機能低下症の診断が確定したら,グルココルチコイド(GC),甲状腺ホルモン(TH),性ホルモン,GHの順に補充療法を加えていく。
GCとしてヒドロコルチゾン(HC)の生理量(1日に10~25mg)を2~3分割とし,コルチゾール日内変動を模するため,早朝に多く配分する。長期にわたるコルチゾール低下が継続したと推測される場合に,初回から通常量を用いるとステロイド精神病を誘発することがある。HCの容量調節として尿中遊離コルチゾールは信頼性に欠ける。症状やQOLを確認しながら,副腎クリーゼを発症しない範囲で高用量を避ける。高用量によって,肥満,高血糖,高血圧,脂質異常の副作用を認める。GCとしてプレドニゾロンやデキサメタゾンなどの合成ステロイドを用いることも可能であるが,HCより半減期が長いため,内臓脂肪の増蓄積,代謝異常,骨粗鬆症の発症の頻度が高まる。分泌刺激検査においてACTH・コルチゾール反応が十分とは言えない軽症者でも,ストレス対応のため少量HC(1日に5~10mg)の補充が必要である。
THとしてレボチロキシンを用いる。12.5~25.0µgの低用量から開始し,血中遊離T4と遊離T3が正常域となるよう調節する。血中TSHは補充量の指標とならない。
性ホルモンとGHは患者によって開始時期は前後するが,同時に開始しても問題はない。性ホルモンは妊孕性を考慮する場合とホルモン補充のみの場合とで異なる。男性の場合,前者ではヒト絨毛性ゴナドトロピンと遺伝子組換えヒトFSHを用いて,血中テストステロンと精子の増加を試みる(いずれも自己皮下注)。後者の場合は,テストステロン筋注を1カ月に1~2回行う。女性の場合,婦人科に依頼し,妊娠希望の有無によって排卵促進あるいはカウフマン療法を選択する(本稿では成人男性のみ記載)。GH治療の詳細は他稿を参照。少量のGHから開始し,血中IGF-1の正常化やQOLの改善を指標に調整する。浮腫,関節痛,高血糖などの発症に注意する。
下垂体近傍の腫瘍性疾患において,手術治療が必要な場合も術前に下垂体機能を評価し,下垂体ホルモンの障害を認めたら,GC補充を行ってから,手術療法へ移行する。

残り841文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する