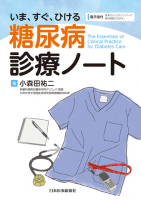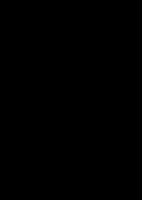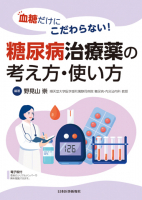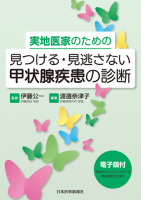お知らせ
2型糖尿病[私の治療]
2型糖尿病は,インスリン分泌低下の遺伝素因に,エネルギー過剰の生活習慣(過食・高脂肪食・運動不足)に起因する肥満・内臓脂肪蓄積によるインスリン抵抗性が加わり,相対的なインスリン作用不足となり高血糖を発症する。
▶診断のポイント
健康診断で,ヘモグロビンA1c(HbA1c)が6.1%以上あるいは空腹時血糖が110mg/dL以上の場合,75gブドウ糖負荷試験を行い,空腹時血糖126mg/dL以上か負荷後2時間血糖が200mg/dLを超え,かつHbA1c 6.5%以上ならば糖尿病と診断する。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
非高齢者において,血管合併症を防ぐための目標値はHbA1c<7.0%である。一方,高齢者では認知機能障害が軽度あるいは基本的ADLが自立している場合はHbA1c<7.0%で,中程度以上の認知症や基本的ADLの低下,多くの併存疾患や機能障害が存在する場合はHbA1c<8.0%とする。重症低血糖が危惧される薬剤〔インスリン製剤,スルホニル尿素(SU)薬,速効型インスリン分泌促進薬〕には下限を設ける。
【専門医のいる施設で多くの薬剤が使用できる場合】
非高齢者か高齢者か,肥満なのか非肥満なのか,さらに腎機能低下(eGFR<60mL/min/1.73m2)・心機能低下(BNP 50pg/mL以上)の有無で場合わけをして,処方を組み立てる。
〈肥満者〉
肥満(BMI≧25)で腎機能低下がない場合は,ビグアナイド薬(メトホルミン),次はSGLT2阻害薬か経口(あるいは皮下注)GLP-1受容体作動薬を投与する。以上の薬剤が使用できない場合は,DPP-4阻害薬を用いる。
〈非肥満者〉
非肥満でインスリン分泌低下が主体の場合にはDPP-4阻害薬,次に速効型インスリン分泌促進薬,少量のSU薬,ビグアナイド薬,SGLT2阻害薬のいずれかを追加する。いずれの薬剤によっても十分にコントロールできない場合には,持効型インスリンを就寝前に4単位から開始する。空腹時血糖値をメルクマールに適宜増量する。
【外勤先などで,薬剤の数が限られている場合】
病態にかかわらずDPP-4阻害薬,次に腎機能や肥満の有無によって追加する薬剤を決める。

残り1,749文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する