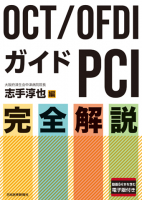お知らせ
【文献 pick up】85歳以上AF例でも抗凝固療法は有用―GARFIELD-AF/Am J Med誌
脳梗塞リスクが一定以上の心房細動(AF)例では、たとえ「85歳以上」であっても抗凝固療法で生存を含む転帰が改善される可能性が明らかになった。多国籍観察研究"GARFIELD-AF"データを年齢別に解析した結果として、米国・ブリガム&ウィミンズ病院のSamuel Z. Goldhaber氏らが10月31日、American Journal of Medicine誌に報告した。
AFは加齢に伴い有病率・CHADS2スコアのいずれも高値となるにもかかわらず、70歳を超えると加齢とともに抗凝固薬を処方されている患者の減少傾向が、わが国でも伏見AFレジストリから報告されている。

【対象】
今回Goldhaber氏らが解析対象としたのは、AFと新規に診断された5万2018例中、「CHA2DS2-VAScスコア(「女性」以外)≧2点」の2万5538例。日本を含む世界35カ国からランダムに選ばれた1318施設から登録された。
「ワルファリン服用歴あり」は除外されている。
2万5538例中、1万8373例が経口抗凝固薬(OAC)を服用し、7165例が非服用だった。
【方法】
これら2万5538例を対象に、OAC服用の有無に伴う24カ月間の「死亡」「非出血性脳卒中・塞栓症」「大出血」リスクを比較した。
比較にあたっては年齢「65歳未満」(1万5691例)、「65-74歳」(1万6946例)、「75-84歳」(1万5252例)、「85歳以上」(4129例)の4群に分けて比較した。
【結果】
その結果、まず「死亡」は「85歳以上」でのみOAC「服用」群における有意なリスク減少を認めた(補正後ハザード比[HR]:0.77、95%信頼区間[CI]:0.63-0.95[vs.非服用]。その他年齢層では減少傾向のみ)。
同様に「85歳以上」では「非出血性脳卒中・塞栓症」リスクも、OAC「服用」群で「非服用」群に比べ有意に低下していた(HR:0.58、95%CI:0.34-0.99)。
「65-74歳」でも同様だった(0.51、0.35-0.76)。
一方、「65歳未満」「75-84歳」では減少傾向にとどまった。
対照的に大出血リスクは、「85歳以上」なら、OAC服用に伴う増加は認めなかった(0.97、0.56-1.68)。
一方、「75-84歳」ではOAC服用に伴い大出血リスクは有意増加となり、「65歳未満」「65-74歳」でも増加傾向を示した。
なお「85歳以上」服用のOACは46.2%がDOACだったが、うち48.9%で承認外低用量が用いられている。
また「75-84歳」「85歳以上」では、「死亡」「非出血性脳卒中・塞栓症」「大出血」リスクのいずれも、DAOCとビタミンK拮抗薬間に有意差はなかった。
【考察】
Goldhaber氏らはこの結果が、「AFに対するOACの有用性は高齢者ほど大きい」と結論する欧州観察研究"PREFER in AF"と軌を一つにするとして、本研究が高齢AF例に対するOAC処方への懸念を払拭する一助となるよう願っているようだ。
本研究は英国Thrombosis Research Instituteから資金提供を受けた。