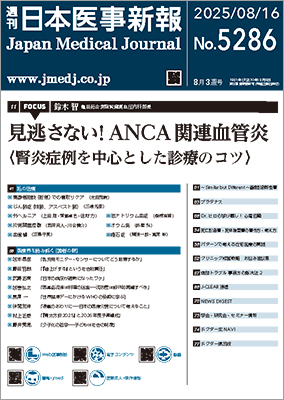お知らせ
喘息外来の病診連携のコツ 【紹介先を患者が決定する病診連携で治療を継続】

【Q】
呼吸器専門外来を受診する喘息患者は,咳喘息などの軽症患者を含めると,いまだ増加傾向にあります。ある程度安定した患者を開業の医師に返すための病診連携のコツを,専門医側だけでなく開業医側からの視点も含めて具体的にご教示下さい。大阪赤十字病院・吉村千恵先生にお願いします。
【質問者】
安場広髙:三菱京都病院呼吸器・アレルギー内科部長

【A】
気管支喘息患者に対して病診連携を行う際,呼吸器内科医を逆紹介医として選択できる可能性は少なく,紹介先に難渋することがしばしば起こります。これは,現在の治療レベルを維持したいという紹介医の考えと,呼吸器内科専門医が他の専門医と比較し極端に少ないという現実が存在するからですが,患者は本当に専門の医師にかかりたいと思っているのでしょうか。
当科では2009年,105人の患者を対象に「あなたにとって望ましいかかりつけ医は? 急性期病院は?」というアンケートをとりました。回答者は「自分の症状をよく理解してくれる」や「自宅から近い」「いつでも診てもらえる」をかかりつけ医に求めており,急性期病院には「専門的な科の最新の医療を受けられる」「救急・時間外・夜間の受け入れがある」と,それぞれの医療機関に違う要望を抱いていることがわかりました。これを参考に当院では,まず紹介先を患者に決定してもらうことにしました。かかりつけ医がいない場合は,かかりつけ医紹介窓口の事務員と相談しながら地域の医療機関のリストアップを行います。その中で患者が決定した医師に事務員から処方継続ができるかどうかを確認し,可能であれば紹介先が決定される仕組みです。
厚生労働省の「喘息死ゼロ作戦」では,課題として病態の認識や標準治療の周知を掲げています。ガイドラインの周知が必要ですが,喘息以外の疾患にも対応されている開業の先生が一から専門外の本を読むのも大変です。そこで,紹介時にお渡しする喘息連携パスには企業が提供するポケットガイドラインを同封することとしました。ポケットガイドラインを同封したパスは好評で,2012年度の調査ではパスを受け取った医師の91%が連携後,「よりガイドラインを参考にするようになった」と回答し,「第一選択薬である吸入ステロイドの処方が増えた」と49%の先生が回答しました。
パスにより,継続の難しい吸入手技も,当院あるいは当院周辺の薬局での再指導で対応することも可能となります。病薬連携,薬薬連携も病診連携を支える大きな柱のひとつです。
切れ目のない病診連携を行うためには,まず患者の希望を聞き,紹介医が非専門の先生方と連携を行っているという認識から始める必要があると考えます。