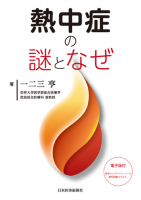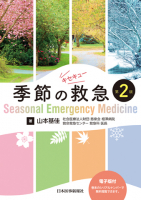お知らせ
ベルリン基準によるARDSの定義

急性呼吸窮迫症候群(ARDS)は,急性の非心原性肺水腫である。静水圧の上昇による間質への溢水ではなく,炎症性変化や血管透過性の亢進による滲出で,酸素化の悪化や肺コンプライアンスが低下する。侵襲に続発する肺の病的反応は,原因や背景が異なっても共通する病像を示すことに着目し,1994年に米国・欧州コンセンサス会議(AE
CC)が定義した(文献1)。急性発症の呼吸不全で,PaO2/FiO2(P/F)比の低下から酸素化障害を,胸部X線の両側浸潤陰影で肺水腫を診断し,肺動脈楔入圧高値で心不全を否定する。単純で使いやすいが欠点もあったため,ベルリン基準で見直された(文献2)。
まず,急性の定義を1週間以内の発症とした。また,両側浸潤陰影を「胸水,無気肺,結節で説明できないもの」として,読影の信頼性を高めるようにした。さらに,肺水腫の鑑別から肺動脈楔入圧の値を外し,心不全や輸液過剰で説明のつかない呼吸不全としている。
一方,重症度について1994年の定義では,P/F比で急性肺障害とARDSにわけた。しかし,急性肺障害がわかりにくいことからこれを外し,P/F比で軽症・中等症・重症に分類する。そして,P/F比は呼気終末陽圧(PEEP)によって大きく影響を受けるため,PEEPを5cmH2O以上で評価することにした。
随所に工夫のみられる改定であるが,予後判定や有効な治療の開発に役立つか否かは,今後の検討が待たれるところである。
【文献】
1) Bernard GR, et al:Am J Respir Crit Care Med. 1994;149(3 Pt 1):818-24.
2) Ferguson ND, et al:Intensive Care Med. 2012;38(10):1573-82.